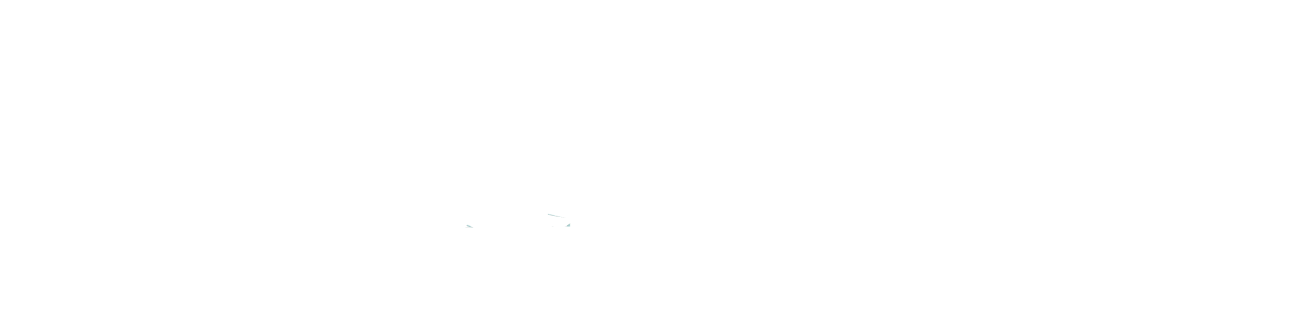
現在ギリシア神話として知られるオリュンポスの神々と英雄たちの物語の始まりは紀元前まで遡る。
鉄器を持つインド=ヨーロッパ語族系のギリシア人が、エーゲ海周辺で栄えていた青銅器文明(キクラデス文明、ミノア文明、ミケーネ文明)に攻め入ったのが紀元前30世紀頃。先住民族により口頭伝承されてきた土着の神々を、ゼウスを主神とする彼らの神話に取り込んだのが始まりだ。
ギリシア神話が神話として体系化されるのは、さらに時代が下った紀元前9~8世紀頃のこと。盲目の吟遊詩人ホメロスがギリシア神話の英雄と戦争を題材に最古にして最初の叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』として伝えたのである。こうした口承でのみ伝わっていた神々の誕生系譜を『神統記』として文字にまとめたのが詩人ヘシオドスだ。次いでギリシア悲喜劇の詩人たちが、神話の世界をより体系的に、かつ強固に築き上げた。
やがてギリシア神話は、ギリシア語とともにローマに伝わり、古代ローマ固有の神話とも重ね合わされることになった。例えばギリシア神話の主神ゼウスが、ローマ神話で同じイメージの神としてユピテルと呼ばれるなどだ。
ところが紀元4世紀。ギリシア神話は、ローマの国教となったキリスト教によりゼウスを主神とする多神教の世界観を否定されることになる。ギリシア神話は宗教ではなく、はっきりと架空の造り話か寓話の類であると見なされるようになったのだ。そのためギリシア神話の復活には15世紀イタリアのルネサンスを待たねばならなかった。
しかしルネサンスが求めた人間らしさこそギリシア神話最大の特徴でもある。ギリシア神話の神々と英雄は極めて人間臭く、物語は愛と冒険と運命の悲喜劇に満ち満ちているのだ。
ギリシア神話の世界は、滅びと勃興を繰り返す没落史観だ。最初の神々が生まれた“黄金時代”、ゼウスが統治する“銀の時代”、人間たちが互いに殺し合う“青銅の時代”、半神半人の英雄ヘラクレスやテセウスが活躍した“英雄の時代”、そして最初の女パンドラが撒き散らした災厄の中、英雄のいない世界で生きることを余儀なくされた人々の“鉄の時代”と、徐々に時代が悪くなっていくという世界観でできている。人類はすでに何度も神によって滅ぼされており、そのたびに時代が移るのだ。
なお、それを記したヘシオドス自身の時代こそが“鉄の時代”の末世であり、ギリシア神話世界観においては“鉄の時代”は今なお続いていると告げている。
オリュンポス山の頂の上空にあるという天界の館に住まう“オリュンポス神族”12柱の王。ギリシア神話の主神であり、天界を統治する天空神とされる。好色な男性神で、数多くの神、妖精、半神、英雄、怪物たちの父。美しい女性(時には少年)に目がなく、変幻自在に姿を変えては、嫉妬深い妻ヘラの目を盗み、精力的に浮気を繰り返した。
時間神クロノスと地母神レアの末子として生まれたが、「天界の王の座を息子によって奪われる」という予言を恐れたクロノスは、生まれた子たちを次々と呑みこんでいた。これを嫌ったレアが、岩を産衣でくるみ、呑ませたことで難を逃れ、羊飼いの家族に育てられることになったという。
成長したゼウスはクロノスの小姓となった。そしてある晩、思慮と助言の神メティスに命じて神々の飲み物ネクタルにからしと塩を混ぜてクロノスに飲ませ、兄弟姉妹を吐き出させることに成功する。その後、クロノス率いるティターン神族との10年にも渡る大戦争(ティタノマキア)に勝利し、その功績から神々の長子となり、くじ引きによって天界を支配することになった。
なお、その戦争の際、ゼウスは父祖ウラノスが地中に封じた巨人キュクロプス、ヘカトンケイルを味方に引き入れ、雷霆(ケラウノス)という武器を授かっている。雷霆は非常に強力で、その後のギガントマキア―大地母神ガイアが放った巨人族ギガスとの戦いにおいても大活躍している。
“先に知る者”という意味の名を持つティターン神族の予言神。粘土を捏ねて人間を作ったともされる人類の祖。クロノスとゼウスの戦争の際には、ゼウスの側について戦ったことでオリュンポス入りを許されたが、人類を愛するがゆえにさまざまな知識を人類に与え、たびたびゼウスの不興を買った。最も有名なのが天上の火を盗み、人類に与えた事件で、火を持たなかった人類はプロメテウスのこの行動をきっかけに文明や技術を発達させ、多くの恩恵を受けることになる。
なお、人間が火を持っていなかった理由には、神々と人間が獣の配分をめぐって争った時にプロメテウスが計略によって人類に肉を、神々に骨と脂肪を取らせたことに怒ったゼウスが人間から火を取り上げたという説や火を得た人類が神々に匹敵する力を持つことをゼウスが恐れたという説などがある。
ともあれ、ゼウスの怒りを買ったプロメテウスは、コーカサス山脈の山頂に磔にされ、生きながらにして毎日肝臓を巨大鷲についばまれるという責め苦を3万年強いられることになった(これを助けたのが半神半人の英雄ヘラクレスである)。
なお、この物語には、いくつかの続きがある。
ゼウスは火を受け取った人類にも罰を与えるため、鍛冶神ヘパイストスに人間の女性を作るよう命令した。そしてその女に決して開けてはいけないと言い含めた壺(あるいは箱)を持たせ、プロメテウスの弟エピメテウス(後に考える者の意)のもとに送り込んだのである。プロメテウスは予言の力でそれを知り、「ゼウスからの贈り物は受け取ってはならない」とエピメテウスに言い含めていたが、エピメテウスは女を嫁に迎えてしまった。やがて女は好奇心から壺(箱)を開け、世界に災厄が撒き散らされることになるのである。これが有名な、災厄の詰まったパンドラの壺(箱)の物語である。
オリュンポス神族の一柱にして冥府の神。オリュンポス十二神には通常数えられないが、それは彼がオリュンポス山ではなく地下世界に住むからであり、オリュンポス神族内ではゼウス、ポセイドンに次ぐ実力を持つ。ゼウス同様クロノスとレアから生まれた子であり、生まれてすぐにクロノスに呑まれたが、ゼウスの機転で復活、クロノスたちティターン神族との戦いではゼウス側についた。
このとき、ゼウスが巨人キュクロプスから雷霆を受け取ったように、ハデスも被ると姿が見えなくなる兜を受け取っている。この兜は次のギガントマキアにおいてはヘルメスに、メドゥーサ退治においてはペルセウスを貸し与えられ、彼らの活躍に貢献した。
冷酷で慈悲を知らない性格とされており、一度冥界へと落ちた死者を決して地上に帰さぬことから、また地下資源の神でもあることから“富める者(プルートーン)”という異名も持つ。
オリュンポスは神々の住む山の名前であり、偉大な12柱の神々の総称だ。ギリシア神話の世界観では、世界は天界、人間界、冥界に分かれており、人間界はさらに地中海によって北方はエウロパ、南方はアジアやエジプトなどに分断されている。もちろん世界の中心はギリシャで、それ以外の海はオケアノスというギリシア人の認知の外にある異郷だった。
そんな狭い世界ゆえなのか、オリュンポスの神々はたびたび人間と接触し騒動を起こしている。地名や言葉の語源となる話も多いが、有名なのがゼウスの浮気とヘラの呪いにまつわる物語だろう。
ゼウスが人間や妖精の女の元に行くのにどのような姿に変身をしたのかや、ゼウスの浮気を知ったヘラの嫉妬によって運命を狂わされた女たちによる怪物たちの誕生秘話は、ギリシア神話の見どころのひとつだ。
呪いの犠牲者たちを憐れんだゼウスが物語の最後で星座に変えて夜空に飾るという結末も、実にギリシア神話らしい。特にオリュンポスの12柱は太陽系の惑星に名づけられるほど天体と関わりも深い。ギリシア神話の神々や怪物、英雄たちが現代でも知られているのは、こうした星座の物語として広く語り継がれた影響も大きいだろう。
ギリシア神話の前半の中心が神々のラブロマンスなら、中盤の見どころは半神半人の英雄たちによる冒険ファンタジーだ。英雄たちが退治する怪物の中には、ラブロマンスの余波で生まれたものもいるので、ある意味、神の後始末と言えるのかもしれないが、それを成すのも神と人間の間に生まれた子たちだった。テセウスのミノタウロス退治、ヘラクレスの12の試練、イアソンとアルゴー号の冒険、オルフェウスの冥界下りなど、有名エピソードも目白押しだ。
その中でもペルセウスのメデューサ退治は、敵も強ければ、神々の助力も多く、メデューサ退治の後に一波乱も二波乱もある大冒険だった。
ペルセウスが退治することになったメデューサは不死身のゴルゴン三姉妹の三女で、髪の毛がすべて蛇でできている女の怪物であった。特質すべきは、見た者を石に変えてしまうという恐ろしい力だ。
そんな怪物が相手なだけに、ペルセウスはアテナ神とヘルメス神から旅立ちにあたって4つの武具を与えられている。アテナ神からは鏡のように磨かれた黄金の楯、空を飛ぶことができる靴、百眼巨人のアルゴスを倒したという新月刀ハルパーを、ヘルメス神からはハデスも使っていた姿隠しの兜を、といった具合だ。
グライアイという3人の老婆に道のりを尋ね、妖精に魔法の麻袋を贈られ、ついにメデューサの眠る沼に到着したペルセウスは、黄金の楯を掲げてメデューサの姿を見ないように首を切り落とした。その首からはペガサスが生まれたという。
メデューサの首を麻袋に入れ、ペガサスに乗って逃げたペルセウスは、その後、いくつかの場所に立ち寄りながら、海岸の付近で岩に縛りつけられた姫を発見することになる。それがポセイドンの怒りを買った王妃のせいで生贄に捧げられることになったアンドロメダ姫であった。ペルセウスは姫を襲おうとしていた一角クジラの海獣ケートスをメデューサの首で石に変えて姫を救い、娶ると、生まれ故郷であるアルゴスの国王になったといわれている。
ギリシア神話のもうひとつの特徴が、予言と避けられない運命という悲劇性だ。
ギリシア神話の後半戦、トロイア戦争のきっかけも、プロメテウスの予言に端を発している。
プロメテウスは「ゼウスが女神テティスと結婚すると父より優れた子が生まれ、ウラノスがクロノスに、クロノスがゼウスに追われたように、ゼウスも王座を追われることになる」という予言をし、ゼウスに浮気を諦めさせた。そのためテティスは英雄ペレウスと結ばれたのだが、その結婚式で事件は起こってしまう。
結婚式に呼ばれなかった嫉妬の女神エリスの策謀によって、ヘラ、アテナ、アフロディーテの三女神の誰が一番美しいかを決める争いが始まったのだ。三女神は審判者であるトロイの王子パリスを買収するため報酬をパリスに提示した。ヘラは“権力と富”を、アテナは“勝利と名声”を、アフロディーテは“最高の美女”を約束し、結果、アフロディーテが選ばれた。パリスはこうして人間の中で一番美しい女性ヘレネを略奪することに成功するのだが、女神の決めたこととはいえ王の妻を奪われたスパルタ軍が黙ってそれを受け入れるはずがない。
このヘレネをパリスから取り戻そうとする戦いが、『イリアス』『オデュッセイア』に描かれるトロイア戦争の始まりになるのである。
そしてもうひとり、このトロイア戦争で予言によって苦しめられた女がいる。それがトロイアの王女カサンドラだ。
カサンドラはアポロン神に求愛され、予言の力を贈られた。しかしそれゆえにアポロン神が自分を捨てて去ってゆく未来まで見てしまい、愛を受け入れることができなかった。これにアポロン神は憤慨。カサンドラの予言は必ず当たるが、誰にも信じられないという呪いをかけたという。
こうしてカサンドラはトロイアとギリシャが戦争をすることやギリシア人が撤退時に残していった大きなトロイの木馬が破滅をもたらすことを事前に知りつつも、その言葉を誰にも信じてもらえないという悲劇に見舞われることになる。
このような、運命に逆らい、しかし流されていく人間の物語を題材にした演劇は、ギリシア悲劇と呼ばれ、今でも知られている。
余談だが、アポロン神はかつてエロスによって恋心をかきたてられ、ダフネという妖精を追いまわすことになり、月桂樹に姿を変えられてまで逃げられたことがある。これもまた、善良なだけや万能に神を描かないギリシア神話らしいエピソードだ。
ギリシア神話の虚構侵蝕の代表格は、なんといっても怪物退治だろう。この場合、ギリシア神話に登場する怪物を観測者たちが倒さなければならなくなるパターンが最も多い。ペルセウスの神話を題材とした虚構侵蝕では、意中の女性をアンドロメダ姫に見立てた虚構核が最終的には一角クジラの海獣に変身したという事件があった。また、企業のセキュリティシステムが虚構核となり、社屋を迷宮化させて、牛頭の怪物ミノタウロスを配置した例もある。簡単なものでは、クイズ出題者がとっておきの謎を出す際に虚構侵蝕を起こし、スフィンクスに変身したというものだ。
難題と解決はギリシア神話の特性なのか、ほかの虚構侵蝕より手軽に試練を与えられがちだ。その一例となるのが、さまざまな精神分析上の用語の語源にもなっている呪いや予言にまつわる虚構侵蝕だろう。
例えば、父親を超えるという野心を持った息子が父殺しの予言を受けたオイディプスの運命を背負い、観測者たちが身辺警護に駆り出されたという事件。あるいは、触れたものがすべて黄金に変わって苦しむミダス王のような虚構核やピュグマリオン王のように無機物への愛を成就させようとした虚構核などもいた。
人間の感情にギリシア神話は容易く名前を付けてしまう。ギリシア神話は広く知られているだけに、ほかの神話とくらべても、虚構侵蝕のきっかけになってしまうことが多いようだ。
なお、苦難に対し、ギリシア神話の神々が直接助力してくれることも過去にはあったようだが、これも安易に受け入れるべきではない。虚構に心を奪われてしまった観測者を神が憐れみ、星座にしてしまったという笑えない話もあるのだから。
| ギリシア・ローマ神話対応表 | |
|---|---|
| ギリシア神話 | ローマ神話 |
| ゼウス | 雷の神ユピテル |
| ヘラ | 結婚と出産の女神ユノー |
| ポセイドン | 海の神ネプトゥーヌス |
| アテナ | 知恵と医療の女神ミネルヴァ |
| アレス | 戦と農耕の神マルス |
| ヘルメス | 商人と旅人の神メルクリウス |
| アポロン | 太陽の神アポロ |
| アルテミス | 月の女神ディアナ |
| アフロディーテ | 愛と美の女神ウェヌス |
| ヘパイトス | 火の神ウルカヌス |
| デメテル | 農耕の女神ケレス |
| ヘスティア | 炉と家庭の女神ウェスタ |
| ディオニソス | ワインの神バッコス |
| ハデス | 冥界の神プルートー |
| ガイア | 大地の女神テルース |
| ウラノス | 天空の神ウラヌス |
| クロノス | 農耕の神サトゥルヌス |
| ペルセポネ | 春の女神プロセルピナ |


『ギリシア神話 神々と英雄たち』(バーナード・エヴスリン 著、三浦朱門 訳/社会思想社)
『ギリシア神話物語事典』(バーナード・エヴスリン 著、小林稔 訳/原書房)
『ギリシア神話の謎』(ムー 謎シリーズ18/学研)
『ギリシア神話』(フェリックス・ギラン 著、中島健 訳/青土社)
『ギリシアの神々』 (ジェーン・E・ハリソン 著、船木裕 訳/筑摩書房)
『ギリシア神話物語』(楠見千鶴子 著/KADOKAWA)
『イリアス』上・下(ホメロス 著、松平千秋 訳/岩波書店)
『オデュッセイア』上・下(ホメロス 著、松平千秋 訳/岩波書店)
『トロイア戦争とシュリーマン』(ニック・マッカーティ 著、本村凌二 監修/原書房)
『ローマ神話 西欧文化の源流から』(丹羽隆子 著/大修館書店)
エジプト神話はナイル川に沿って発展した古代エジプト文明が生み出した古い神話だ。エジプト神話は、ナイル川上流の上エジプト、下流の下エジプトがそれぞれに発展し、その広大で気候も異なる土地で数多くの部族が太陽、月、動植物や虫などを守護神として崇めたところから始まっている。
しかし紀元前32世紀、上エジプトのナルメル王が下エジプトを倒し、エジプトは統一された。文化が交じりあい、上エジプトの神話は下エジプトの神話の影響を受けることになったのである。
また、長い歴史を持つ古代エジプトでは、31の王朝が興亡を繰り返した。そのため神々も、そうした背景から位置づけを変えられたり、習合されることになっていった。
エジプト神話と一口に言っても、大きく分けて主神や創世神話の異なる4つのグループが存在する。上下エジプトの統一前から存在するヘリオポリス神話とヘルモポリス神話、紀元前27世紀以降に生まれたメンフィス神話、紀元前16世紀以降の中王朝期に信仰されたテーベ神話である。
エジプト神話はひとつの神話体系としてみるには矛盾に満ちている。それは創世神話や神の序列が都市や時代によって異なるからだ。
一方でエジプト神話には、都市の守護神が実は姿を変えているだけで同じ神であるという考えも根づいている。例えばヘリオポリス神話の主神はアトゥムだがラーでもあり、メンフィス神話の主神ブタハ、テーベ神話の主神アメンもすべてラーであるという具合だ。
とはいえ、世界が原初の水から生まれたとする創世神話や、太陽を崇め、肉体を保存しておけば死者が生前の姿で蘇ると信じているなど、重なる物語も多い。動物の顔に人間の体を持つ神々の存在も、エジプト神話を象徴する特徴だろう。
なお、多神教として知られるエジプト神話には、一時期、世界初の一神教を始めた歴史がある。有名なツタンカーメン(トゥトアンクアメン)の父、アメンホテプ4世の時代だ。ラーを中心としたヘリオポリス創世神話に代わり、ヘルモポリス神話が作られると、創世神の一柱であったアメンが主神となり、その神官たちは強大な権力を有した。都市国家テーベを中心にアメン大司祭国家と呼ばれる勢力にまで成長し、ファラオとエジプト国内を二分したのである。
そのためアメンホテプ4世は、唯一神アテンを主神に据え、宗教改革を行なった。自らも“アテン神に有益なる者”を意味するアクエンアテンへと改名し、王朝発祥の地テーベをも放棄したのである。
アクエンアテンはアメンにかかわる神の名を神殿から削り取り、神像を破壊するなどして迫害したとされているが、今ではほかの神々の存在を積極的に否定しなかったという説が優勢となっている。
とはいえ、この宗教改革は、ほぼ一代で終わってしまった。後継者と定めたスメンクカーラーの死後、彼もまた数年で亡くなり、結果として次の王ツタンカーメンの治世でふたたびアメン神への信仰復興が行なわれたのである。アクエンアテンは後世の人々から異端者と見なされ、彼が造営した建物も徹底的に破壊された。名前すらも碑文から削除されたという。
このようにエジプト神話は王朝の権力争いの影響を大きく受けている。神話の出来事とされる事象も実は人の世で起きた出来事の隠喩なのかもしれない。
エジプト神話の太陽神。ヘリオポリス九柱神の一柱。
その日課は太陽の運行であり、毎朝、天空の女神ヌトからスカラベの頭をしたケプリとして生まれ、日中はハヤブサの姿、あるいは太陽の船“マンデト”に乗って空を移動する。ただし、この旅では朝と夕に大蛇アポピスに襲われるため、ただひとりアポピスに怯まない破壊神セトに守ってもらっている。夜は雄羊の姿アトゥムとなり、夜の船“メセケテット”に乗り換え、死んだ人間の魂である星々を従えて冥界ドゥアドを照らしながらヌトの口に入る。そして朝になるとふたたびヌトからケプリとして生まれるというサイクルを繰り返している。
最高神として絶大な権力を持っていたが、後の時代には無能な年老いた神として軽んじられるようになった。やがて人間が自分の敵になると信じ込むようになり、人間を滅ぼすため、自らの右目を雌ライオンの頭を持つ破壊の女神セクメト(怒りにとらわれた女神ハトホルとされる場合もある)に作り変えたこともあったようだ。また別の神話では、ホルスに権力を与えようとしたイシスが、ラーの唾液を含んだ泥から作った毒蛇にラーを咬ませ、解毒の代償として魔力と真名を聞き出したという話もある。
エジプト神話の冥界の王。死と復活の神。ヘリオポリス九柱神の一柱。
神々の長兄であり、女神イシスとの間に天空神ホルスを成した。後に弟神のセトに謀殺されるが、即位中は人々に小麦の栽培やパンやビールの製造を教えたとされる。もともとは植物の再生を神格化した神であったが、やがてナイル川の氾濫と植物の再生が死を克服する力の象徴とされて王の復活にかかわる重要な神となったようだ。
オシリスの死は、妻のイシスを魔術や再生の女神とする由来にもかかわっている。オシリスはセトに棺を贈られ、閉じ込められてナイル川に流された。イシスはオシリスの棺を探しに出かけ、シリアのビブロスで棺を見つける。しかし棺の中でオシリスは溺死。セトはさらに見つかった遺体を14の断片に刻み、エジプト中にバラまいてしまった。イシスはその断片を妹のネフティスとともに集めてまわり、オシリスとネフティスの子アヌビスとともにミイラにして、復活の儀式を行なう。ただし性器だけは魚に食べられてしまっており、戻せなかった。そこでイシスは魔術によって性器を再生し、ホルスを生んだとされている。
復活したオシリスだったが、一度死んだ身であるからとエジプトの王から退き、冥界で死者の審判を監督する冥界の神になったとされている。
エジプト神話の知恵を司る神。神々の書記。時の管理者。医療の神。楽器の開発者。暦(太陰暦)の守護神。
その姿は、トキかヒヒのどちらかで表される。
基本的には中立の立場であり、神々の争いでは調停役を務める。死者の審判においては、死者の生前の行ないを記した書を持ち、アヌビスとともに死者の罪を計量する天秤の傍に立つ。
生まれについては諸説あり、ヘリオポリス神話においては世界ができた時に自らの力で石から生まれたとする説が有力。そのほかにもセトの頭を割って誕生した、オシリスの末弟という神話もある。
ヘルモポリス神話では主神。言葉で宇宙に秩序を与え、宇宙に法則を生み出したと言われている。原初の水から生まれ、一致団結して天地を創造した8神“オグドアド”の4男神(カエル)と4女神(ヘビ)の主であり、創造神。ラーもオグドアドの生んだ卵から誕生させている。
その力はオシリスやホルスとも互角であり、オシリスたちが生まれる際には、月との賭けに勝ち、時の支配権を得た。魔法にも通じ、女神イシスにも数多くの呪文を伝えたようだ。また人々にピラミッドの建造方法などを与えたのもトートだとされている。彼の書いた42冊の魔法の書物『トートの書』には、この世のあらゆる知識が収録されているとされる。ギリシア神話ではヘルメス神とも同一視された。
エジプト神話最古の創世神話は、原初の水(海)ヌンから始まった。ヌンから、自らの意志で自身を作り出したのが創造神のアトゥムだ。アトゥムは創造の仕事をするにあたり、ヌンを退かせ、原初の丘ヘリオポリスのベンベン石に降り立った。アトゥムがくしゃみをすると鼻孔から乾燥した空気の神シューが現われ、唾を吐くと口から湿気の神テフヌトが生まれた。この2柱が最初の夫婦神となったとされている。
アトゥムは夫婦を海を渡る旅へと送り出すと、さまざまなものを心に描き、原初の水から動植物や鳥を生み出した。この時、アトゥムは調和の女神マアトやアトゥムの目となる女神ハトホルも作り出している。
アトゥムに送り出されたシューとテフヌトは、大地の神ゲブと天空の女神ヌトを生んだ。ゲブとヌトは交わり星々を生んだが、しかし交わったまま一時も離れなくなってしまった。そこでシューがヌトを高く持ち上げ、ゲブとヌトを引き離した。これにより、天と地が分かれ、太陽の通り道と人間の生活する空間が確保されたのである。
しかしヌトは引き離される前に子を宿していた。だが1年のうちのどの日にも子どもを出産できないという呪いもアトゥムからかけられていた。それは生まれる子どもたちが災いを生むと予言されていたからとも、嫉妬したシューの仕業だったとも言われている。
そこでヌトは知恵の神トートを頼った。トートは月と賭けをして勝ち、時の支配権を手に入れる。そして5日間の閏日を勝ち取り、この間にヌトはオシリス、セト、イシス、ネフティスという、もっとも偉大な9柱の神(エネアド)のうち残る4柱を生み落としたのである(オシリスとイシスの息子ホルスと習合された大ホルスを含めて5柱とする説もある)。
エネアドからはオシリスがエジプトを統治する王となった。またアトゥムも、太陽神ラーと同一視され、アトゥム・ラーとなった。
なお、エジプト神話の最初の人間は、シューとテフヌトを探しに出たハトホルが、戻った際に自分に代わる目がアトゥムの顔についていることに気づき、自分の場所を奪われたと泣いた時の涙から生まれたとされている(年老いたラーの涙から生まれたとする説や創造神クヌムによって粘土から作られたとする説もある)。その後、アトゥムはハトホルを自分の眼窩に戻した。ハトホルはコブラの姿になってアトゥムの世界支配を手伝ったという。
古代エジプトでは独自の死生観により、人は死後、冥界(ドゥアト)への旅を経て、楽園アアルで復活すると信じられていた。ドゥアトは地上から姿を隠した神々が住む場所であり、ラーの太陽の船も毎夜ここを通り、朝には地上に出る。エジプトでは世界も人も同じように死んで蘇るというサイクルの中にあると考えられていたのである。
エジプトの死生観によれば、人は死ぬと、いったん魂が分かれ、冥界で復活を遂げるとされた。ただ、冥界で復活するにも肉体が必要だったため、遺体をミイラにして死者の魂が戻れるよう保存した。また、死者のために“死者の書”や“ウジャド(ホルス)の目”などの護符や副葬品を用意し、「開口の儀式」という死後も五感を使えるようにする儀式も行なったという。
これらはすべて、冥界での旅路の安全や来世の生活のためであった。死者は、数々の試練が待ち受ける冥界の旅に出ると、ミイラ作りの神アヌビスに“二柱のマアトの広間”に導かれ、冥界の神オシリスの審判を受けることになるのだ。
死者はかつてオシリスがそうされたように42柱の神々の前で、生前の行ないについて無実を誓わなければならなかった。その後、心臓を抜き取られ、“真理を司る女神マアトの羽根”と天秤にかけられる。悪事を犯したものは心臓が重くなるため、羽根と釣り合いがとれなくなるのだ。罪人は心臓を怪物アメミットに食べられ、永遠に復活できなくなるという。こうして、このオシリスの審判を乗り越えた死者だけが、楽園アアルの野に向かうことを許されるのである。
アアルの野の死者は、生前と変わらない暮らしをし、呪文を唱えればバー(魂)として現世に戻れると信じられていた。名前にも魂の一部が宿っていると信じていた彼らが本当に死ぬのは、肉体も墓も朽ち、名前さえも消されてしまった時なのだ。
なお、これらの物語は、当初は死後オシリスとなるとされた王にのみに必要なものだったが、時代が下るにつれ、多くの階層の人々に知られていったようだ。
ファラオとは一般的に古代エジプトの政治的、宗教的最高権力者を指す。そしてエジプト全土を治める天空神ホルスの化身であり、死した際には冥界の支配者であるオシリスにもなる。後世には太陽神ラーの代理人ともされた神権政治の頂点だ。
その背景には、かつてエネアドたちの間であった王権を巡る争いがある。破壊神セトとホルスの、エジプトの王を決めるための戦いである。この戦いは80年にも及んだとも、実はまだ終わっておらず世界の終わりまで続くのだとも言われている。
戦いのあらましはこうだ。
先代のエジプト王オシリスを謀殺した弟セトは、オシリスの妻イシスを捕らえて収容した。やがてイシスがホルスを生むと、毒蛇に襲わせてホルスを殺害しようとするが、トートの手により救い出されたホルスは、セトの知らぬところで育てられることになる。
やがて成長したホルスは、セトへの復讐に燃え、オシリスの子としてエジプトの継承権があると主張するようになった。トートをはじめとする神々は承諾したが、セトは認めず、またラーも太陽の運行時、セトの力に頼っていたこともあってか経験不足を理由にホルスの主張を却下した。
そこで神々は正当な後継者がどちらなのかを話し合うことにした。一方で、ホルスを王にするためのイシスの策謀もすでに始まっていた。
当初イシスはこの会議への介入を却下されていた。そこでイシスは老婆に化けて会議に潜入し、さらに若い女性に化けてセトに身の上相談を持ちかけたのである。言葉巧みに「父の財産は息子が継ぐべきだ」という発言を引き出されてしまったセトは、自己矛盾に陥って怒り、巨大な豚に姿を変えてホルスを襲った。この蛮行に裁判官であるラーは怒って退廷したが、ホルスの妻ハトホルのとりなしで会議は再開されることになる。
次に行なわれたのが、セトとホルスがともにカバに変身して川に潜り、先に陸に上がった者が負けという勝負だった。この時もイシスは暗躍し、釣り針でセトを引き上げようとしている。しかし、誤って釣り針をホルスに引っかけてしまったり、セトに引っかけ直した際も「お前は俺の妹だろう」という言葉に動揺して釣り針を落としてしまうなど失敗は続いた。その結果、裏切られたと早合点したホルスによりイシスは首を刎ねられてしまう。イシスはラーの計らいで復活したが(雌牛の頭を置いて代用とした)、暴挙に出たホルスは罰としてセトに目玉を山中に埋められたのだった。
視力を失ったホルスはハトホルの治療を受けることになる。そして眼窩にカモシカの乳を与えられ、目を復元したホルスは、その後もセトと激しい戦いを繰り広げるのである(トートが月の力を借りてホルスの左目を癒したという説もある)。
最後の戦いは、石の船での競争だった。この時セトは石の船を作ったが、ホルスは杉の木で船を作り、漆喰で覆って石の船に見せかけた。そのため競争が始まるとセトの船だけが沈んだ。セトはカバに変身して水中からホルスを引きずり込もうとする。しかしホルスは槍を使って逆襲。勝利し、父の仇討ちを果たしたのであった。
ホルスの王権は法廷でも認められ、神々の知るところとなった。これ以来、地上を統治する王ファラオは、ホルスの化身と見なされるようになったのである。
エジプト神話では、すべての時間がマアト(創造神によって最初に定められた宇宙の秩序)によって調整され、繰り返されると考えられている。太陽が昇っては沈むという一日の周期だけでなく、世界の始まりから終わりもまた、繰り返される大きな時間なのだ。だからこそ、その1周目である神々の時代の出来事は、人間の時代にも繰り返されると信じられている。
神々の物語が現実で繰り返される。まさに虚構侵蝕だ。そのためエジプト神話の虚構侵蝕は、神話をなぞるように再現される例が多い。今さら古代エジプト文明への逆行を求める人間はそう多くないだろうが、親から子への相続問題、兄弟の確執、死と再生など人間の本質に根差した思いは虚構侵蝕を生み出すのに十分な理由となる。それがエジプト神話と結びつけば、虚構世界に獣の頭を持つ神が現われてもおかしくはない。
また明確な悪しき神がいるというのもこの神話の特徴だ。正義を執行したい虚構核が敵を求めた結果、黒幕や敵役をエジプト神話の神々が請け負ったというパターンもある。獣面の神々は明らかに異質な存在であり、分かりやすい異教なのだろう。だが相手は神である。簡単に勝てるはずもない。もしかしたら、砂の中から現われる古代の遺跡は、神に敗れ、ドゥアトで審判を受けて心臓を食われた軽率な虚構核が残した虚構の残滓なのかもしれない。


『エジプトの神々』(池上正太 著/新紀元社)
『エジプトの神々』(J・チェルニー 著、吉成薫、吉成美登里 訳/六興出版)
『エジプト神話集成』(杉勇、屋形禎亮 訳/筑摩書房)
『神々と旅する冥界 来世へ』(松本弥 著/弥呂久)
『新版増補 古代エジプトの神々』(松本弥 著/弥呂久)
『図解世界の神々と神話』(神話雑学研究会 編著、中村了昭 訳/成美堂出版)
『世界の歴史〈2〉古代オリエント』(岸本通夫、伴康哉、富村伝、吉川守、山本茂、前川和也 著/河出書房新社)
『世界のミイラ』(近藤二郎 監修/宝島社)
『世界の神話伝説図鑑』(井辻朱美 監修、フィリップ・ウィルキンソン 編、大山晶 翻訳/原書房)
北欧神話とは文字通り北欧に伝わる一連の神話群だ。
紀元1世紀前後、歴史家タキトゥスは、彼が“高貴な野蛮人”と呼んだローマ帝国の外縁に住むゲルマン人について、その慣習、性質、社会制度、伝承などを『ゲルマニア』として書き記した。そこにはすでに、ゲルマン人がヴォーダン(オーディン)を最も崇拝していると書かれている。
しかし現在伝わる北欧神話は、このゲルマン神話とは区別されるものだ。ゲルマン人の神話は4世紀後半のゲルマン民族大移動によりローマ化、キリスト教と同化して独自性を失い、急速に姿を消していったのである。
そのため現在、北欧神話として知られている物語は、北欧に残ったスカンディナヴィア人とアイスランド人に起源を持つものとなっている。8世紀後半から11世紀初頭にかけて、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、すなわち古代スカンディナヴィア人のヴァイキングたちは、外洋航海船を使い、西欧海岸を侵略していた。
彼ら古代スカンディナヴィア人は、ゲルマンの土着の神話を継承し、ルーン文字を発展させたが、口伝伝承の伝統により、それらを文書にまとめようとはしなかった。キリスト教化以前の神話を書き留めたのは8世紀頃の修道士たちであり、多くは13世紀になって初めて記録されたものなのである。また、この頃にはスカンディナヴィア人もアイスランドに入植していたため、彼らの物語はアイスランドの作家によってまとめられることになった。
その中で最も偉大な文学作品がスノッリ・ストルルソンの『散文のエッダ』である。そこに古ノルド語で書かれた作者不詳の『古エッダ(詩のエッダ)』が加わり、北欧の一族の神話は一応の完成を見た。
北欧神話もまた、ほかの神話同様、自然現象を物語により説明したものだ。アイスランドの火山や氷河に囲まれたスカンディナヴィア人はそんな自然を背景に灼熱と極寒の世界から始まる創世神話を作り上げたのだろう。
厳しい自然とヴァイキングの闘争の性質は北欧神話にも大きな影響を与えている。その特徴は、世界の終わりである最終戦争を描いていることだ。
神々の黄昏と呼ばれるその最終戦争は、ヴァルヴァと呼ばれる巫女が主神オーディンに語った予言という形で綴られたものである。つまりまだ起こっていない出来事なのだ。しかも予言では、この戦争で北欧の神々はことごとく死に絶え、世界は滅亡し、生き残った者たちだけが住む世界が再生すると語られている。
北欧神話の主神にしてアース神族の最高神。魔術と狡知の神。男神ボルと女巨人のベストラの間に生まれ、兄弟とともに原始の巨人ユミルを殺害して世界を創造した。しばしば人間の世界を旅しており、その際はつば広の帽子を目深にかぶり、青いマント(あるいは黒いローブ)を羽織った長い髭の老人の姿を取る。
愛馬は八本足のスレイプニル。武器は魔法の槍グングニル。フギン(思考)とムニン(記憶)というワタリガラスを眷属とし、2羽にさまざまな情報を持ち帰らせている。また、足元にはゲリとフレキという2匹の狼がいる。オーディンには食事の必要がないため自分の食物はこの狼たちに与え、ワインのみで生きているとされているようだ。
詩文の神でもあり吟遊詩人のパトロン。また戦いの神で、戦死者エインヘリヤルをヴァルハラに送るので戦死者の父とも呼ばれる。しかし自ら先頭に立って戦うというよりは、戦乙女ヴァルキュリアを戦場に差し向けて勝敗の運命を支配したり、気に入った者に必殺の陣形を授けたりと、知恵と策略と魔術の加護を与えることが多かったようだ。
彼の知識に対する貪欲さは異常なほどで、目的のためには女性を誑かしたり、己の身を傷つけることさえも厭わなかった。知識を得られるという泉の水を一口飲みたいと巨人ミーミルに頼んだ際には、片方の眼球を代価に求められて応じ、以来、片目になっている。また、知識のために自身を生贄に捧げたこともある。9日9夜、グングニルに突き刺されたままユグドラシルの木で首を吊って(逆さ吊りとする説もある)得たのが魔法の言葉であるルーン文字だ。また飲めば誰でも詩人や学者になれる詩の蜜酒を奪うため、奴隷同士を戦わせたり、巨人の娘と関係を持つこともあった。
こうした彼の貪欲さは、息子バルドルの死や最終戦争ラグナロクを予言されてから、いっそう強いものになっていく。またラグナロクでの援軍となる戦死者を集めるため、人間の世界に不和をばら撒くようにもなっていった。オーディンは最終戦争ラグナロクではフェンリル狼に飲みこまれる運命にある。息子のヴィーザルが父の仇を討つが、世界の再生後もオーディンが復活することはない。
北欧神話に登場する悪戯好きの神。善と悪の両面を持つ北欧神話最大のトリックスター。神々の敵である霜の巨人(ヨトゥン)の血を引くが、オーディンと義兄弟の契りを交わし、アース神族の一員となっている。
美しい容貌をしているが性格が悪く、いつも悪知恵を働かせて神々を困難に陥れる。女巨人アングルボザとの間には、後々神々の脅威になる大蛇ヨルムンガンド、巨狼フェンリル、冥府の女王ヘルをもうけた。
その一方でオーディンの槍グングニルや雷神トールの鎚ミョルニル、巨大な帆船スキーズブラズニルなどを作らせて神々に貢献する一面も見せている。
また彼は巨人スィアチの指示で永遠の若さを約束する黄金の林檎の管理人だった女神イズンを誘拐したことがある。この迷惑行為はイズンとともにリンゴが失われ、アースガルズの神々が年老いるという大事件に発展したが、最後にはイズンの奪還を手伝っている。
ほかにも石工に変装した山の巨人が人間の住む世界“ミズガルズ”を壁で囲む報酬として月と太陽と女神フレイヤを要求した際に、神々の代表として交渉役になり、条件を出したこともある。しかし条件が達成されそうになると、作業を遅延させる妨害を行ない、結果的に巨人の企みを防いだりもした。
そんな彼が、完全に神々の敵となった転機は、不死身のバルドルの死であった。バルドルの弟、盲目のヘズをそそのかし、唯一の弱点であったヤドリギ(ミスティルテイン)を投げつけさせたのである。
さらにロキは、バルドルの復活も悪戯によって阻止した。バルドルの弟のヘルモーズが死の国ヘルヘイムで女王ヘルに生き返らせてくれと頼んだ際、ヘルは「世界中のすべてのものが彼のために涙を流すならばバルドルは生者の国に戻ってもよい」と約束した。そこでアース神族は世界中に使者を送り、あらゆるものにバルドルのために泣いてくれるように頼んだのである。
すると本当に全世界のあらゆる生物、無生物が泣いてくれたのだが、たった一人、女巨人セックだけが泣かなかった。このセックの正体が実は変身したロキであり、神々の宴に乱入したロキは、そのことを明かすとともに集まっている神々の過去の罪や恥辱を一人ずつ暴きたて罵倒したという。
このことから彼は神々の怒りを買い、捕らえられたロキは、息子ナリの腸で巨岩に縛られ、洞穴に幽閉されることになった。そこは蛇の毒液が滴り落ちるため、妻のシギュンが器を持って防ぐほかない場所だ。
そのため器がいっぱいになり、彼女が捨てに行く間だけは頭に毒液が当たり、ロキは苦痛のあまり叫び声を上げるのだという(その影響で地震が起きるとされている)。こうして決定的にアース神族から離反したロキは、ラグナロクにおいて戒めがはずれると、巨人族を率いてアース神族を滅ぼす戦いに出陣する。そして角笛ギャラルホルンを持つ光の神ヘイムダルと戦い、相打ちになるのである。
天地創造の前。混沌とした世界にはギンヌンガ・ガプという深淵と、灼熱の世界ムスペルヘイム、極寒の世界ニヴルヘイムだけが存在していた。やがてニヴルヘイムの冷たい霜にムスペルヘイムの熱風が触れると、その雫から両性具有の巨人ユミルと牝牛アウズンブラが生まれた。ユミルはアウズンブラの乳で育ち、寝汗をかいた左脇からは男女の霜の巨人が、両足が交わると6つの頭を持つ巨人がそれぞれ生まれたという。
一方、アウズンブラが塩辛い氷の塊を舐めていると中から神々の祖となるブーリが現われた。ブーリは名のない霜の巨人と交わりボルを産み、ボルは巨人ボルソルンの娘ベストラを娶って、この夫婦からオーディン、ヴィリ、ヴェーの3兄弟の神が生まれた。
オーディンたちは増え続ける霜の巨人が好きではなかった。やがてその感情は憎悪に変わり、ついにユミルを殺害したのである。
3兄弟はギンヌンガ・ガプを血で満たすと、ユミルの屍体を浮かべて大地とした。また、骨、歯、毛髪などで山、岩石、樹木を作り、脳で雲を、頭蓋骨で天空を作り出した。さらにムスペルヘイムの火花から太陽と月、星を作り、海辺で拾ったトネリコとニレの木からは人間の男のアスクと女エンブラを作ったのである。
オーディンは2人に生命を、ヴィリは精神を、そしてヴェーは視覚と聞く能力、話す能力を与えたという。住まいはユミルのまつ毛で造られた巨大な塀に囲まれた、世界樹ユグドラシルの9つの層のひとつ“ミズガルズ”を与えた。
なお、霜の巨人たちは、世界にあふれたユミルの血により、ほぼ溺死している。生き残った巨人はベルゲルミルとその妻だけで、この2人から巨人はふたたび数を増やすことになる。
神々と光の妖精はユグドラシルの天上、アースガルズ、ヴァナヘイム、リョースアールヴヘイムに住むことになった。ユグドラシルは9つの層(宇宙)に分かれており、オーディンたちは天上を前述の3つ、地上をミズガルズ、巨人たちの国ヨトゥンヘイム、小人たちの国スヴァルトアールヴヘイムに、地下をムスペルヘイム、ニヴルヘイム、そして死の国ヘルヘイムとした。
しかし世界を支えるユグドラシルは、常にさまざまな災いに苦しめられている。ユグドラシルは天上、地上、地下それぞれに根を下ろしているが、地下では大蛇ニーズヘッグが根を齧り、天上の枝では牡鹿や山羊が新芽や若葉を食べているのだ。
有名なヴァルハラはアースガルズのオーディンの宮殿にある。ヴァルハラには、ヴァルキュリアによって集められたエインヘリアルたちがおり、彼らはここでラグナロクに備えた大規模な演習を毎日行なう。
この演習では敗れた者も日没とともにふたたび蘇り、夜は大宴会を開き、翌日にはまた演習を行なうことができるという。そのためヴァイキングたちの間では、死後ヴァルハラに迎えられることこそ戦士としての最高の栄誉とされていた。
北欧神話の神々はアース神族、ヴァン神族、ヨトゥン(霜の巨人)の3種類に分類されている。アース神族とヴァン神族は、かつて人間からの貢物を受け取る権利を巡って争ったが、後に講和し同化していった。
アース神族とヴァン神族による世界最初の戦争は、ヴァン神族の女神グルヴェイグが呪歌と舞踊の魔術「セイズ」を使い、悪い女たちに性的な悦びをもたらしたことがきっかけとなった。アース神族はグルヴェイグを槍で突いたり、火で焼いたりして殺そうとしたが、グルヴェイグは3度蘇り、殺すことができなかった。
しかしこの仕打ちに怒った海の神ニョルズの率いるヴァン神族は決着をつけるため、ウルズの泉でアース神族と対峙。主神オーディンが槍を投げたことで戦争が始まったのだ。
戦いは長く続き、神々は人質を交換することで和解することにした。ヴァン神族はニョルズとその息子フレイ、娘フレイヤ、さらに賢神クヴァシルを人質として差し出したが、アース神族が人質として差し出したのは、優柔不断な神ヘーニルと彼を補佐する巨人ミーミルだった。
これに怒ったヴァン神族はミーミルを殺し、その首をアースガルズへ送り返した。その後、両神族は同化し、ともに人間の貢物を受け取るようになった。
ラグナロクは北欧神話における世界の終わりである。
オーディンが受けた巫女の予言では、まず神々の場所が朝焼けや夕焼けによって赤く染まり、太陽が暗く天候の悪い夏が続くことが語られている。光の神バルドルの死により、太陽の現われない夏が3度訪れ、風の冬、剣の冬、狼の冬と呼ばれるフィンブルヴェト(恐ろしい冬、大いなる冬)が始まるのである。
この日、すべての封印、足枷と縛めは消し飛ぶことになる。束縛されていたロキやフェンリル、ヨルムンガンド、ガルムなどは解き放たれ、これに呼応した巨人たちもアースガルズに攻め込んでくるのだ。
これを察したヘイムダルが角笛ギャラルホルンを吹き鳴らし、その音はすべての世界に響き渡る。オーディンが聞いて備えていた予言がついに現実になったのである。
太陽と月はフェンリルの子であるスコルとハティに飲み込まれ、星々は天から落ちていく。山は崩れ、地は割れ、人々のモラルも崩壊して、地上の生き物の大半はヘルの元へ行くことになる。
海からは巨蛇ヨルムンガンドが陸に迫る。死者の爪で造られた船ナグルファルには巨人フリュムと死者の軍勢が乗っている。ムスペルヘイムからは巨人スルトが炎の剣レーヴァテインを持って進む。
スルトには炎の巨人ムスペルの子らが続き、彼らはアースガルズとミズガルズを結ぶ虹の橋ビフレストを破壊する。
集められた戦死者たち、エインヘリアルは、ヴィーグリーズの野で巨人の軍勢と激突する。オーディンはフェンリルに立ち向かうが、フェンリルに呑まれて死亡。オーディンの息子ヴィーザルが、フェンリルの下顎に足をかけ、その体を切り裂き、父の仇を討つ。
トールはヨルムンガンドと戦い、ミョルニルで殴り倒すが、毒を喰らい、9歩退いて倒れる。戦神テュールは死者の国の番犬ガルムと相打ちになる。ロキとヘイムダルも相打ちになる。
フレイは勝利の剣を失っていたため、スルトとは鹿の角で戦うしかなく、打ち倒されるだろう。そして最後に残ったスルトが炎の剣を投げ、世界樹ユグドラシルを焼き尽くす。炎と煙が噴き上がる中、大地は沈没し、世界は滅びるのである。
しかしその後、海中からは緑なす大地が現われるとも予言は語っている。生き残ったアース神族は輝く野イザヴェルに集まり、バルドル、ヘズも死者の国より復活する。
オーディンの子ヴィーザル、ヴァーリ、トールの子モージ、マグニ、さらにヘーニルらは生き残り、新たな時代の神となる。さらに焼け残った森には、炎から逃れたリーヴとリーヴスラシルという人間も生き残っている。
彼らこそラグナロク後の人類の祖となる男女だ。
比較的歴史が浅く、さまざまなファンタジー作品の元ネタにもなっている北欧神話の虚構侵蝕は、一見してフィクションの虚構侵蝕と見分けがつきづらい。後世の作家たちが作り出したフィクションの影響を受け、新たな定義に神話の怪物や登場人物のほうが寄せられているケースが数多く見られるほどだ。
だがそれは本質的には神話の虚構侵蝕とは似て非なるもの。そうした虚構侵蝕なら、むしろ神話を探るよりメディアミックス作品を探ったほうが解決が早まることもあるだろう。北欧神話の虚構侵蝕では多くの場合、侵蝕後の世界の雰囲気や敵対する虚構体の特徴を見て虚構核が北欧神話の何から影響を受けたかを探るほうが有益なのだ。
だが原点ともいうべきヴァイキングたちの遺物などが虚構核となった場合だけは話が別だ。
そもそも、初期の北欧神話は生贄を捧げる信仰形態を持っていた。さらに言えばそんな神々を信仰していたのは荒々しい侵略者ヴァイキングたちなのである。フィクションで見た神々がそこにいたとしても、彼らがヒーローでない可能性は十分に高く、血生臭い結末も起こり得る。何しろバーサーカー(ベルセルク)と称される狂戦士の原点もこの北欧神話なのだから。
また、戦場の具現化や9つの世界のいずれかへの変化もよく報告されている。名剣グラムでファフニールを倒した竜殺しの英雄シグルドの例もあるように、怪物退治も北欧神話の虚構侵蝕の定番だ。
火の国や極寒の国、巨人たちの国など、世界の特徴がはっきりしていることも、虚構核が虚構世界を構築しやすい要因だろう。
戦場の場合は戦乙女ヴァルキュリアが現われることもある。彼女たちはルーン文字の魔術などを使って観測者たちを支援してくれはするが、多くの場合、観測者がヴァルハラに迎え入れられるべき戦士かどうかを注意深く見定めている。もし観測者が彼女たちのお眼鏡にかなってしまったら、戦いの後、虚構世界に連れ去られる可能性を警戒しなければならないだろう。
なぜなら観測者が戦場から消えた例は、北欧神話の虚構侵蝕後ではよくあることらしいのだ。VER-THの掲示板での、ヴァルキュリアとともに援軍として現われた虚構体のエインヘリアルが、かつて仲間だった観測者によく似ていたという報告は、今でも語り草になっているほどである。


『図解北欧神話』(池上良太 著/新紀元社)
『英雄列伝』(鏡たか子 著/新紀元社)
『図説北欧神話の世界』(W.ラーニシュ 著、吉田孝夫 訳/八坂書房)
『北欧神話』(キーヴィン・クロスリイ・ホラン 著、山室静、米原まり子 訳/青土社)
『北欧神話と伝説』(ヴィルヘルム・グレンベック 著、山室静 訳/講談社)
『図解世界の神々と神話』(神話雑学研究会 編著、中村了昭 訳/成美堂出版)
『世界の神話伝説図鑑』(井辻朱美 監修、フィリップ・ウィルキンソン 編、大山晶 翻訳/原書房)
『神の文化史事典』(松村一男、平藤喜久子、山田仁史 編/白泉社)
『世界の神話百科:ギリシア・ロ-マ/ケルト/北欧』(アーサー・コットレル 著、松村一男、米原まり子、蔵持不三也 翻訳/原書房)
日本の神話の代表格が記紀神話であることに異論を挟むものはいないだろう。記紀神話が『古事記』と『日本書紀』、つまりは天地開闢から神の誕生、日本の成立、歴史を綴った神話の書であることは疑いようもない。特に『古事記』は、全体の三分の一が神話で構成され、数多くの神が登場するのが特徴だ。そのため歴史書であると同時に出雲神話を語る文学としての価値も非常に高いとされている。
しかし一方で『古事記』編纂の目的が、唐(中華王朝)からの独立と朝廷の正統性を示すためであったことは隠しようもない。それゆえ日本最古の正史とされる『日本書紀』と読みくらべてみると、朝廷に不都合な歴史が描かれておらず、意図的に活躍を省かれている人物も多いのだ。
そもそも『古事記』は、7世紀後半から8世紀初め、天武天皇が自ら選んだ歴史と神話を稗田阿礼に覚えさせ、その言葉を後に編纂させたのが始まりだった。その成り立ちからしても偏った視点から語られている物語だということは念頭に置かねばならないだろう。
つまり記紀神話は日本の神話を語る上で極めて大きな役割を果たすが、それだけをもって日本の神話、民間伝承のすべてとすることはできないのである。
例えばお伽噺だ。今でこそ子どもに語って聞かせる昔話や民話として知られているが、これらもまた歴史が長く、12世紀には日本最大の古説話集『今昔物語集』が、14~16世紀頃には『御伽草子』などがまとめられている。桃太郎や浦島太郎などの誰もが知る昔話、あるいは中国から伝わり日本独自の発展を遂げた織姫と彦星の七夕伝説やひな祭りにまつわる由来なども日本という国の伝統を語る上で欠かせない要素となるだろう。
20世紀まで下れば、さらに小泉八雲の『怪談』、柳田國男の『遠野物語』など日本各地に伝わる伝説、幽霊話などが民話ブームの中で広く知られてくる。
こうして掘り起こされた怪異、妖怪の伝承もまた日本独自の神話と考えて異論はないはずだ。もっと深堀するなら『東日流外三郡誌』『竹内文書』『九鬼文書』など戦後に騒ぎを起こした偽書も、日本の神話に含められるかもしれない。日本各地にある都市伝説にすら、すでに日本独自の昔話として語られているものがあるのだから。
もちろん語られた内容がすべて真実とは限らない。明らかな捏造もあるに違いない。だが、そんな誰もが嘘と分かって語る物語の中にこそ、もしかしたら『古事記』の語らぬ日本古来の神話や伝承が隠されているのかもしれない。
日本の天津神が住まう高天原の主神にして太陽神。農耕神、機織神などの神格も持つ。
日本の国土を生み出した男神イザナギが国産みによって亡くなった妻イザナミに逢うため、黄泉の国に向かい、現世へと逃げ戻った後、黄泉の汚れを払うために禊を行なった結果、イザナギの左の目から生まれたとされている。イザナギは、同じように生まれた神々の中でも天照大神が最も貴い神と定め、高天原の統治を命じた。
有名なエピソードとしては天岩戸隠れの伝説があげられる。イザナギの鼻から生まれた乱暴者の弟神スサノオが織女を殺害したことに悲憤した天照大神は、岩屋の奥に引きこもり、入り口を大岩で塞いだ。その結果、世の中が闇夜となり、農作物も育たなくなったというのだ。困り果てた八百万の神々は事態解決のため知恵の神思兼神を頼った。
神々は思兼神の指示のもと、岩屋の前で鶏を鳴かせたり、鏡や玉を作らせて祝詞を奏上したりし、さらに天鈿女命を岩戸の前で踊らせた。そして外の騒ぎに気づいた天照大神が岩戸を少しだけ開けたところで「天照大神よりも高貴な神がお出で下さいました」と鏡を見せ、身を乗り出した瞬間に岩陰に身を潜めていた怪力の天之手力男神が引っ張り出すとともに、やはり隠れて待機していた天太玉命が岩戸に注連縄を張って退路を断ったのである。
こうして世にふたたび太陽が戻ったという、いかにも太陽神、農耕神らしい神話だ。
記紀神話においてはあくまで高天原の主神であり、日本全土の最高神ではなかったが、今では多くの国民に信仰され、国土の最高神となっている。
高天原から天降った神々、国津神たちの主神とされる国作りの神。大地の神、商業の神、開発の神など多様な神格も持つ。
スサノオと奇稲田姫の子孫にあたり、荒ぶる八十神を平定して国の礎を築いた後、天照大神の孫にあたるニニギに国を譲ったことで知られる。
スサノオの荒々しい性格を受け継いだ兄神(八十神)たちと違い、柔和な性格で、因幡国に住む八上比売に求婚に向かった際も荷物持ちとして最後尾を歩いた。その際、皮を剥かれて泣いている一匹のうさぎを助け、その予言により八上比売への求婚に成功するも、兄たちの恨みを買い、二度謀殺されている。
その後、神産巣日神の協力によって蘇生したが、追手から逃れる中で黄泉の国の王となっていたスサノオと対面。スサノオの娘である須勢理毘売と互いに一目惚れして想い合うようになった。
スサノオに繰り返し試練を与えられた大国主神は、やがてスサノオ秘蔵の神器を持って須勢理毘売と駆け落ちするが、追ってきたスサノオに「その大刀と弓矢で八十神を下して王となれ」と激励され、出雲を平定。国津神の王となったそのあと、少名毘古那神と協力して国を治めていたが、天津神に国を統治させたいと考えた天照大神に対し、出雲大社の建立を条件に国を譲ったとされる。
記紀神話や伝統的な民話などに登場しない謎の神。
足の健康を願う神として現代でも全国各地の神社でひっそりと祀られている。遠くの異郷から旅してきた客人神として扱われるが、その正体については箒神、龍神、蛇神、塞の神、製鉄の神など諸説がある。
偽書『東日流外三郡誌』の影響により、縄文の神、蝦夷の神、遮光器土偶のイメージとしても世間に広まった。
巨石信仰とストーンサークルを結びつけて宇宙人とする説、古代シュメールの天空神アヌンナキが変化したものとする説もあるようだ。
『古事記』の語る日本の創世神話は渾沌とした世界から姿形すらも朧気な5柱の別天津神が出てくるところから始まる。
その後、神世七代と呼ばれる陽神(男神)と陰神(女神)が現われ、その中のイザナギとイザナミが国作りを任されたのである。
イザナギとイザナミは別天津神より天沼矛を預かり、天浮橋に立って渾沌とした地上をかき混ぜた。この時、矛から滴り落ちたものが積もってオノゴロ島になったとされている。
オノゴロ島に降り立ったニ神は、そこに“天の御柱(天を支える柱)”と“八尋殿(広い御殿)”を建て、男女として交わることにした。
天の御柱の周囲をイザナギが左回りに、イザナミが右回りに巡り、出逢ったところで声をかけるというものだ。しかし女性であるイザナミから誘うのは正しい交わりではなかったため、最初に生まれた子は不具の子、水蛭子だった。二神は水蛭子を葦船に乗せて流し、ふたたび同じ手順で交わったが、次に生まれたのも泡のような姿であった。
悩んだ二神は別天津神に理由を尋ね、呼びかけ順を逆にするという助言を受ける。
こうしてついに淡路島が生まれ、二神は続けて四国、隠岐、九州、壱岐、 対馬、佐渡、本州(大八島)を生んで、日本列島を形成したのである。
国産みが終わると二神は森羅万象の神を生み始めた。
しかし最後に生まれたのが、火之迦具土神という火の神だったため、イザナミは陰部を焼かれて死去。火之迦具土神は、怒ったイザナギに天之尾羽張で首を落とされたが、その死体からもさまざまな神が生まれたという。
死んだイザナミを取り戻すため、イザナギは黄泉の国へと向かった。しかしイザナミはすでに黄泉の食べ物を口にしてしまっており、戻ることができなかった。とはいえ、夫が迎えに来たのだから帰りたいと考えたイザナミは、黄泉津神たちと話し合うことにする。イザナギは、話し合いの間は「決して覗いてはいけない」というイザナミからの条件を受け入れ、待つことに。しかし、いつまで経ってもイザナミが帰って来ないため、つい約束を破ってしまった。
イザナギが見たのは、腐敗して蛆にたかられ、頭、胸、腹などに八雷神を抱くイザナミの姿だった。
イザナミの姿を恐れたイザナギは地上に逃げ出してしまう。自身の朽ち果てた醜い姿を見られたイザナミも、八雷神と黄泉醜女にイザナギを追わせる。
この逃走劇は、イザナギが逃げる途中で髪飾りや櫛をブドウやタケノコに変え、あるいは黄泉の境に生えていた桃の木の実を投げて、黄泉醜女がそれを食べている間に逃げるという方法で続けられた。そして黄泉の国と地上との境である黄泉比良坂の出口を大岩で塞いだところでイザナミ自身に追いつかれるも、イザナギはどうにか地上へと脱出できたのである。
その際イザナミは、岩の向こうから「人間を1日1000人殺す」と宣言。対してイザナギは「それならば私は産屋を建て、1日1500人の子を産ませよう」と言い返したという。
こうして地上に戻ったイザナギは、黄泉の国の穢れを落とすため、禊を行なった。そこからもさまざまな神が生まれた。最後に、左眼から天照大神、右眼から月読命、鼻からスサノオの三貴子が生まれたという。イザナギは、天照大神に高天原の統治を命じ、月読命には夜の国を、スサノオには海原を統治させることにしたのだという。
高天原を追われたスサノオの子孫、大国主神が出雲を治めて後、新たな日本の統治者として天から降り立ったのが天照大神の孫ニニギであった。
ニニギはさっそく木花之佐久夜毘売を娶ったが、一緒に嫁いできた姉の石長比売は追い返してしまった。木花之佐久夜毘売が繁栄の象徴であったように、石長比売は永遠の象徴。そのためニニギとその子孫は、永遠の命を失ったとされた。
そんなニニギたちの子孫が神武天皇であり、神話はここから人間の時代へと移り変わる。
記紀神話には、神武天皇が東征し、大和政権を樹立。その子孫であるヤマトタケルが遠征して東国を平定したと語られている。しかしこれら討伐の伝承はいわば天照大神の流れを汲む天津神系の子孫と大和政権に顧みられなかった土着の神々、国津神との対立の歴史の記録でもある。もともと地上にいた国津神は貶められて妖怪や怪異になったという説もあり、彼らの物語は今や別の形で日本の物語の中に息づくのみだ。
このような語られない歴史は、一般的に正史に対して偽史と呼ばれる。例えば偽書のひとつ『東日流外三郡誌』にはアラハバキ神や邪馬台国についての記述があり、古代の津軽(東日流)地方にあった民族が大和朝廷を間接支配していたと主張している。『東日流外三郡誌』はもはや偽書という扱いが大勢を占めるが、日本各地には真偽の明らかでない語られぬ神話がまだまだ残されているだろう。
神々の世界からは少し離れるが、民衆によって口承されてきた文学の中にも、神々のように信仰を集めているものがある。
例えば狐。民間伝承において、狐は稲荷神の使い、あるいは眷属とされ、しばしば神と同一視されてきた。
例えば天狗。本来は流星を指す言葉だったが、山岳信仰と習合し、今では山の神としての信仰を集めている。河童や鬼も同様だろう。元は妖怪変化でありながら河伯信仰や仏に帰依した八部鬼衆とも結びつく。
昔話に目を向ければ、動物や器物が恩返しに来たり、復讐したり、嫁になったりもする。物を大切にするという日本人的な感覚もある種の信仰といえるだろう。
ならば当然、人間そのものも信仰の対象になる。特に民間伝承には天女や動物、架空の生物たちとの間に子を成したという逸話も多く、そうして生まれた者は立身出世に繋がる特別な物語を背負うことが多い。
日本人に馴染み深いところでいえば、金太郎が例として挙げられるだろうか。金太郎伝説には、母親として山姥が登場する作品が多く、雷神の子供を孕んで産まれてきたとするものや、山の頂上で赤龍が子を授けたというものなどさまざまな出生譚がある。幼い頃から動物たちを友とし、森を守っていた金太郎は、成長すると坂田金時と改名して頼光四天王のひとりとなったのだ。彼は四天王とともに酒呑童子や土蜘蛛を退け、死後も倶利伽羅権現として祀られている。
もちろん、金太郎は伝説上の人物だ。モデルとなった人がいた可能性はあるが、実在は疑われている。だがそれでも、日本各地には金太郎ゆかりの地があり、その扱われ方は神に対するものと変わりはしない。
日本在住の観測者にとって最も身近な神話の虚構侵蝕が日本神話であることに異論はないだろう。
日本では神社や仏閣、あるいは豊かな自然が生活の身近にあるため、虚構侵蝕も地域に根ざした神や妖怪の物語として顕現する傾向が強い。
最も多いのが、虚構核が身近な神社の祭神を参照して、神としての姿で顕現するパターンだ。
地元の住民ならばその地域にある神社の祭神の名前や謂れ、逸話などを知る機会も多いだろうし、感情的共感を得やすいのかもしれない。それこそ神社にお参りした結果、“困った時の神頼み”が虚構侵蝕のきっかけになった例などいくらでもある。過疎によって忘れられた神社が虚構核となり、祭神の姿を取って在りし日を虚構世界として再現することもあるだろう。
名前が知られ、なじみ深い神としては、天神様こと学問の神菅原道真や武道の神建御雷神、芸能の神天鈿女命などが挙げられるだろう。こうした特定の願い事のために祈願される神は特に、虚構核の願いを叶えるため、虚構体として顕現しやすいらしい。
とはいえ、日本の神には世界の神々のような強力な武力を持つ神はそう多くない。顕現したとしても、避けて通れないわけではないだろう。
むしろ怖いのは呪いのほうだ。
例に挙げた菅原道真ももとは怨霊だし、ヤマトタケルが山の神に呪い殺されたという逸話は、日本の神々の得意分野が何であるかを知らしめている。あの悪名高き平将門の首塚の逸話もこのカテゴリだ。
なお、こうした人の呪いに関わる虚構侵蝕では呪いの原因となった時代を追体験させられることが多く、疑似的に解決することで、まるで祟りの沈静化のように虚構侵蝕も解除されることが多い。
しかしこうした怪談話も日本神話の一部でしかない。
伝承として語り継がれていただけのお話も、現代では漫画やアニメ作品の題材になることで昔以上に物語に輪郭を与えられている。人魚の肉を食べて不老不死になった八百比丘尼の伝承、世にある多様な“見るなのタブー”なども、すっかり日本神話の虚構侵蝕の常連だ。こうした虚構侵蝕は昔は解決が難しかったのか、辺境の村には残滓として“本物”が今でも残されていることもあるらしい。有名な河童のミイラなども、解決し損ねた虚構の残滓の名残だ。
昔話といえば、桃太郎や鶴の恩返しなどの物語も思い出される。こちらも近年、映像化されたことで虚構侵蝕の発生が増えた例だ。
だが、フィクションではなく神話題材から発生した虚構侵蝕の場合、さすが本家というべきか、製作者の手心や時代のフィルターがかかっていない分、“本当は怖い昔話”として再現されることがあるらしい。見極めが重要だろう。
いうまでもなく、現代の日本人は神話や宗教を意識することなく、それらを日常の習慣の中に落とし込んでいる。だからこそ虚構侵蝕も同じように現実にするりと入り込んでくる。
偽書とされている古文書も、もしかすると過去の観測者が残した虚構侵蝕される前の正しい歴史書だったのかもしれない。神話や伝承に記されていない神々こそが、かつての日本神話の主神だった可能性もある。
だからこそなのだろうか。偽書愛好家や偽書そのものが虚構核となった虚構侵蝕には、どこか歴史を正しい姿にふたたび上書きしようとする何かの意志が感じられる。
となれば観測者とはいったい何を守っているのだろうか。
もしかしたら偽史を信じる者たちは、今も現実を上書きしようと、虚構侵蝕の発生を待ちわびているのかもしれない。


『八百万の神々 日本の神霊たちのプロフィール』(戸部民夫 著/新紀元社)
『日本の神々 多彩な民族神たち』(戸部民夫 著/新紀元社)
『図解 いちばんやさしい古事記の本』(沢辺有司 著/彩図社)
『マンガ 面白いほどよくわかる! 古事記』(かみゆ歴史編集部 編/西東社)
『遠野物語』(柳田国男 著/新潮社)
『ガイドブック 日本の民話』(日本民話の会 編/講談社)
『偽書『東日流外三郡誌』の亡霊: 荒吐の呪縛』(藤原明 著/河出書房新社)
『偽書が揺るがせた日本史』(原田実 著/山川出版社)
『謎の神アラハバキ―騎馬遊牧民族と古代東北王朝』(川崎真治 著/六興出版)
『面白いほどよくわかる古代日本史』(鈴木旭 著/日本文芸社)
『古代日本の歩き方 その謎を解明する!』(瀧音能之 著/青春出版社)
『歴史人物怪異談事典』(朝里樹 著/幻冬舎)
今でこそ道教を中心に、仙人、精霊、自然神、天体、神格化された祖霊や英雄なども神話体系に組み込んで語られる中国神話だが、かつての中国は神話なき国とされがちであった。というのも孔子の『論語』に「怪力乱神を語らず」という言葉がある通り、中国では巫術や迷信、理屈で説明のつかない怪しげなことは語らないという思想が強く、20世紀初頭に改めてまとめられるまで神話、伝説、神仙譚などは民間伝承や小説の中に断片的に留まるのみだったのである。
もちろん古代中国にも、地域ごとにアニミズムやシャーマニズムのような先祖伝来の神話はあった。世界四大文明の黄河・長江文明が栄えた地でもあるから、洪水神話などは氏族ごとにあったようだ。だが、殷王朝による統一の中で、神話は一氏族のものだけが「正史」として選別され、しかも殷の滅亡によってその伝承すらも失われてしまった。古代中国が早くから歴史の時代に入っており、神話を必要としなかったというのも、神話が軽視された原因のひとつだろう。
中国の古代神話研究の第一人者である袁珂が断片的にしか伝来していなかった文献を系統づけてまとめあげたのは20世紀になってからだ。紀元前5世紀~紀元3世紀にかけて加筆され続けた最古の地理書『山海経』で明らかになった原始山岳信仰、清代前期の短編小説集『聊齋志異』の神仙、幽霊、妖狐などにまつわる怪異譚、『点石斎画報』に描かれた鬼神、迷信、俗習の記録、そして今や誰もが知っている『封神演義』や『西遊記』などの冒険譚、七夕伝説として知られる織女と牽牛の伝説も、最近になって発掘された中国の民間伝承を由来とするものなのである。
なお、中国では早くから官僚制が発達したためか、神話の世界にまでそうした制度が投影されているのが特徴だ。後に中国神話の系統として重視される道教でも、インドから偶像崇拝の文化とともに伝来した仏教の影響から、天界や仙界に住まう神や仙、鬼のいる死の世界などに中国神話独自の世界観を作りあげている。
別名を道徳天尊。道教の始祖とされる中国春秋時代の哲学者老子が神格化された道教の最高神格・三清の一柱。地上では崑崙山に、天上では道教における最高天のひとつ、太清境に住む。
前漢時代までは道(タオ)思想の祖、あるいは神仙の祖とされたが、時代が下るにつれ、宗教的な神へと変貌していった。
『西遊記』では、暴れる孫悟空を捕らえるなどの活躍もしているが、本人の出番はさほど多くなく、金角と銀角が太上老君の金炉と銀炉の番をしている童子とされたり、武器を奪い取る光る輪・金剛琢を持つ青牛怪がもともとは太上老君から逃げ出した乗り物だったなど、箔付のように名を使われることが多い。孫悟空の武器、如意金箍棒の製作者でもある。
中国の四大奇書小説『封神演義』に姜子牙という名で登場する闡教の道士。
仙人になるための修行のさなか、師の命令で崑崙山を下り、周の文王の子、武王の軍師となった。
この時代は狐狸精・妲己に操られるままに暴政を行なう殷の紂王が統治する世であり、姜子牙はその興亡に関わる365人を神の役職に封じる役割を負っていた。なお、『封神演義』には奇想天外な仙人の武器、宝貝(パオペエ)が登場するが、太公望の武器はその中でも最強とされる打神鞭である。
打神鞭は、封神が予定されている365人にしか効果がなく、しかも合計で84人の敵しか倒せない武器ではあるものの、掛け声とともに投げるだけで自動追尾して敵の頭蓋を砕くことができた。太公望の由来は、太公(周の祖)が望んだ賢人に出会えたことを喜んだ周の文王の言葉から。姜子牙が釣り好きだったため今では釣り人の代名詞にもなっている。
中国神話の天地開闢は、宇宙に巨大な卵形の物体だけがあったというところから始まっている。卵の中は陰陽が混沌としており、そこから盤古という角のある毛むくじゃらの巨人が生まれたという。
盤古が斧を振りかざして卵をふたつに割ると、卵の中身は陰と陽に分離した。暗く重いものは下に落ちて大地となり、軽く明るいものは漂って天となり、それを1日に9度姿を変えて成長する盤古が拡げ、天地を分離したのだ。
後に盤古が亡くなると、その死体の各部位からは万物が生じた。その後、兄妹神による人類の創造と三皇五帝の統治が行なわれ、夏、殷、周、秦の王朝の諸侯はそうした伝説の聖王たちの子孫とされた。
一方で、道教の創世神話は、類似点はあれどこれとは異なる。当初の世界は陰も陽もない虚無であり、やがて清濁が分かれ、天地が分かれ、万物が生じた。
そんな万物の中でもっとも貴い存在とされたのが人であり、その中に現われた最初の神が道教の教主にして道(タオ)の化身である太上老君であったようだ。同時に36の天界とその上層に三清境という神界が生じ、そこに道教の最高神・三清(元始天尊、霊宝天尊、道徳天尊)が臣下とともに住まうことになったという。
こうした神界と人界を取り結ぶのが、天界に住まう天帝だ。天帝は人格神であり、あらゆるものを観察し、万物を見通す全知全能の力を持つ。地上の王はこの天帝の代理人であり、国家統一を天に報告する“封禅の儀”などは王だけに許された特権だった。
中国神話を題材にした虚構侵蝕の多くは、やはり仙人、妖怪、宝貝が騒動の中心となる事件だ。あらゆるものに神(魂)が宿る(これは万物が盤古から生まれたため)とされる中国神話では、器物や動物も仙人になりうる。
そうした背景から動物や器物が虚構核となった場合、仙人の姿を取ることが多いようだ。妖怪の場合は日照り神や疫病神、獣人として出現するパターンも確認されている。
桃源郷や龍宮といった異世界や三国志や封神演義、西遊記の豪傑、妖怪たちが現われるのも、中国神話の虚構侵蝕に見られる特徴と言えるだろう。


『中国の神話伝説』(袁珂 著、鈴木博 訳/青土社)
『図説 中国の神々 道教神と仙人の大図鑑』(エソテリカ別冊/学研プラス)
『中国妖怪・鬼神図譜 清末の絵入雑誌『点石斎画報』で読む庶民の信仰と俗習』(相田洋 著/集広舎)
『封神演義』(八木原一恵 編訳/集英社)
『西遊記 キャラクターファイル』(三猿舎 著/新紀元社)
『三国志 きらめく群像』(高島俊男 著/筑摩書房)
『三国志演義』(羅貫中 著/KADOKAWA)
『山海経 中国古代の神話世界』(高馬三良 訳/平凡社)
『道教の世界』(窪徳忠 著/学生社)
『道教とはなにか』(坂出祥伸 著/中央公論新社)
古代ケルト人は、もともとヨーロッパ東部のドナウ川上流の草原に住んでいた騎馬民族だとされている。青銅器時代に西方から移動し、鉄器を持ってヨーロッパ全土に散らばっていったのが、彼らのルーツだ。
ケルトとは、前5世紀のギリシア地理学者がアルプスより北に住むバルバロイを“よそ者、優れた者”を意味する“ケルトイ”と呼んだことに由来する。このうち現在のフランス、ドイツに住んでいたケルト人が「大陸のケルト」、ブリテン諸島に住んでいたケルト人が「島のケルト」と呼ばれる。
ケルトの文化は、紀元前1世紀まで栄えたが、ゲルマン人の圧迫を受けたケルト人の一部は西方に押し戻され、やがてユリウス・カエサルらによって征服されてローマ化していった。“大陸のケルト”はキリスト教の影響を受けて変わり、昔ながらのケルト人の信仰はアイルランドの“島のケルト”に残されたのである。
当初のケルト神話は、終末思想こそあったものの、人格を持つ人間的な神のいない自然崇拝だった。呪い詩を歌う詩人が尊重され、祭祀はドルイドと呼ばれる神官が王の隣に立って行なった。人身御供の伝統もあったようだ。彼らの宗教観は、魂は不滅であり、死後は別の存在に生まれ変わるというものだ。彼らにとって死は休息だったのである。それゆえ死を恐れない彼らの凶暴さはローマ人にひどく恐れられた。
また彼らは書き記したものを信用せず、言葉、発話そのものに力が宿ると考えていた。そのため口伝を重視し、文字資料を残さなかった。
ケルトの文化が文字資料として残されるようになったのは11世紀以降のキリスト教の修道士たちによってだ。そのため現在知られるケルト神話には、キリスト教的影響が色濃く反映されている。
また16世紀に入ると活版印刷によってカエサルの『ガリア戦記』が世に知られるようになり、イギリス人やフランス人にケルト人は自らのルーツとして理想化された。
こうして、ケルトの英雄物語を縦糸に、愛や不倫、名誉、冒険、探求、予言などの騎士物語を横糸にして、後期のケルト神話はキリスト教の影響を多分に含んだアーサー王伝説へと引き継がれていくのである。
トゥアハ・デ・ダナーン(ダーナ神族)の太陽神。光輝くほどの美男子で、武芸、学問、医術、金属工芸から芸術まで万能の能力を持つため、ラム・ファタ(長い腕)やイルダーナ(百芸)とも呼ばれている。
温厚で家族には愛情深い反面、敵対者には容赦がない。ダーナ神族の王ヌアザより王位を譲り受け、フォモール族との戦いに勝利。後に英雄クー・フーリンの父親となった。
ウェールズ、ブリテンの伝承に登場する伝説の王。サクソン人の侵略を迎え撃った英雄。冒険好きで、戦士たちにとっては気前のいいパトロンであり、数多くの魔法の武具を持っている。
12世紀以降は中世騎士道的な理想像を与えられ、アーサー王とキャメロットの円卓の騎士の物語が完成すると、ヨーロッパ中に理想の君主像としてその存在が伝播されていった。エクスカリバーの伝説、聖杯探求の伝説などを残し、死後は湖の乙女たちに導かれ、アヴァロン島で眠りについているとされている。
アイルランドの建国神話は5つの種族が西の果てエリン(現在のアイルランド)に上陸して興亡を繰り返すという内容だが、神話の中心となるダーナ神族は4番目にやってきた種族だ。ダーナ神族の王であったヌアザは、3番目の入植者フィル・ボルグ族(巨人族)との戦いに勝利したものの、右腕を失ってしまった。
肉体に欠損があると王位につけない掟により、ヌアザは退位することになるのだが、次に王位を継いだのはダーナ神族とフォモール族の混血児であるブレスだった。
しかしブレスは怠惰でケチで王としての適正も皆無。重税を課せられて苦しんでいた神々は、ヌアザが義手を得て復位すると、これを歓迎した。
だが、王位を追われたブレスの手引きで、ダーナ神族は続いて邪眼を持つ王バロール率いるフォモール族と戦争をすることになってしまう。しかもこの戦いでヌアザはバロールに敗れてしまった。
そこでヌアザに後を託されたのがルーだった。
ルーもまたバロールを祖父とするフォモール族とダーナ神族の混血児だったが、生まれた直後にバロールに殺されかけたため、ダーナ神族の神々の元で育てられていたのだった。そこでさまざまな技術を学んで育ち、フォモール族との戦いに馳せ参じたのだ。
指揮官となったルーは、バロールの邪眼が自分のほうを向いた一瞬を狙い、石で頭部を貫いた。
こうしてダーナ神族は勝利した。だが、次の5番目の入植者ミレー族(アイルランド族)との戦いで力を失い、地下へと姿を消すことになる。彼らの逃げ延びた世界こそが常若の国ティル・ナ・ノーグだ。神々は妖精になったのである。
ケルト神話の虚構侵蝕は、妖精、ドルイド、アーサー王伝説、異界訪問、魔道具、誓約がキーワードとなるだろう。石に刺さって抜けない“王の選定の剣”を巡っての虚構侵蝕は多いし、よく知られた物語だからか、不倫や三角関係が虚構侵蝕のきっかけになる例も多い。
妖精を観たい、妖精に会いたい、妖精になりたいという純粋な思いから虚構侵蝕が発生した場合にケルト神話がベースになるパターンもあるようだ。しかし妖精といっても種類は多く性質もさまざまだ。善良な妖精に当たればいいが、たいていの場合ひどい目に合うのがオチだろう。
誓約に関しては、ほぼ間違いなく虚構侵蝕の解除方法に直結している。神話において誓約を破った英雄が非業の死を遂げたように、虚構核にも誓いを破らせれば、事件解決の糸口になるかもしれない。
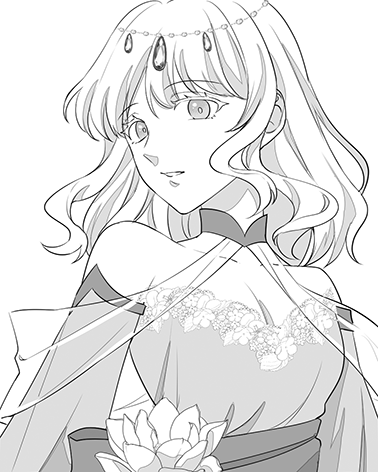

『ケルトの神話 女神と英雄と妖精と』 (井村君江 著/筑摩書房)
『アーサー王物語』(トマス・マロリー 著、井村君江 訳/筑摩書房)
『新訳アーサー王物語』(トマス・ブルフィンチ 著、大久保博 訳/KADOKAWA)
『図解ケルト神話』(岩上良太 著/新紀元社)
『妖精学入門』(井村君江 著/講談社)
『図解世界の神々と神話』(神話雑学研究会 編著、中村了昭 訳/成美堂出版)
『世界の神話百科:ギリシア・ロ-マ/ケルト/北欧』(アーサー・コットレル 著、松村一男、米原まり子、蔵持不三也 翻訳/原書房)
『世界の神話伝説図鑑』(井辻朱美 監修、フィリップ・ウィルキンソン 編、大山晶 翻訳/原書房)
インド神話とは明確な開祖をもたないインド発祥の民族宗教の総称だ。ヨーロッパから侵入したアーリア人が先住のドラヴィダ人に代わってガンジス川流域に定住したのが、インダス文明が崩壊した紀元前15世紀以降のこと。そのアーリア人の神々と土着の自然神への信仰が混交してできたのが、ヴェーダ神話を奉ずるバラモン教であった。
ヴェーダ神話は、デーヴァ神族とアスラ神族への賛歌である『ヴェーダ』を聖典とした祭祀を中心とする教義だった。その最大の特徴は、司祭階級バラモン(ブラーフマナ)が自らの権力を強固にするために使った教義だ。ヴァルナ(階層身分制度)、いわゆるカースト制度を維持するのに、この神話体系は実に都合がよかったのである。
そんなバラモン教も、ほかの階級の経済発展や儀式の形骸化への反発により衰退し、再構成されていく。そうして生まれたのがブラーフマナ・ウパニシャッド神話である。後のヒンドゥー教にも引き継がれる梵我一如(ぼんがいちにょ)の思想や輪廻転生の教えが含まれているのが、この神話の特徴だ。
だが、改革はこれだけでは終わらなかった。支配地域の拡大や階層支配を否定する仏教やジャイナ教の台頭により、バラモン教はさらなる変化を余儀なくされたのである。
こうしてインドの神話は、支配地域の多様で異質な土着の神々の伝承をヴィシュヌやシヴァに取り込み、ヒンドゥーとなっていった。ヒンドゥーとはサンスクリット語のシンドゥに由来し、河、特にインダス河を指す言葉で、つまりインダス河周辺の人たち、インド人という意味だ。
バラモンたちの主神であるブラフマーに、ヴィシュヌ、シヴァを加えた三神は、本来一体であるが、三つの姿で現われる三神一体(トリムルティ)としたのだ。これが現在のインド神話の中心となっているプラーナ神話である。
プラーナ神話における最高神のひとり。黄色い衣をまとった青黒い肌の4本腕の男性で、維持を司る。
ヴェーダ神話起源の古き太陽神で助けを求める人々に救済をもたらす正義の神とされた。4つの手にはそれぞれ、ノコギリ歯のチャクラム“スダルシャナ”、棍棒“カウモダキ”、法螺貝“シャンカ”、蓮華を持つ。
最大の特徴は動物や人の姿を取る化身(アヴァターラ)。中でも重要な10の姿(ダシャーヴァターラ)は、世の中のダルマ(正義・道徳)が衰えアダルマ(不道徳)がはびこるそれぞれのユガ(世界期)に、不道徳を行なうものたちを滅ぼすための特別な化身とされている。
『ラーマーヤナ』においてはラーマ王子として、『マハーバーラタ』ではアルジュナ王子の従者である知恵者クリシュナとして出現した。終末(カリ・ユガ)においては白馬に跨った英雄、あるいは白い馬頭の巨人カルキとして出現し、悪魔カリを倒すとされている。
妻は美と豊穣と幸運の女神ラクシュミー。千の頭を持つナーガの王アナンタや聖鳥ガルーダを乗騎とする。
プラーナ神話における最高神のひとり。破壊と再生を司る。頭に三日月、額に第三の目を持ち、三叉の槍を携えた男性で、恵みを与えるシャンカラと破壊を示すバイラヴァという二面性を持つ。また舞踏の神であり、芸術の神であり、ヨーガの守護神であり、子授けの神。
ヴェーダ神話に登場する暴風神ルドラとも同一視されており、さまざまな権能を持つ(ヴィシュヌと異なり、さまざまな古い神々がひとつの神格へと融合された結果であるとする意見もある)。またその両目は太陽と月で、閉じると世界を闇に包む。そして第三の目は開くと炎を噴き出し、周囲を焼き尽くす。
妻はシヴァの最初の妻サティの生まれ変わりである金色の肌の女神パールヴァティー。乗騎は乳白色の牝牛ナンディン。ナンディンはシヴァが舞う際には、音楽を奏でてくれるという。
プラーナ神話の聖典ともされる叙事詩『ラーマーヤナ』は、ヴィシュヌの化身であるラーマ王子が、羅刹王ラーヴァナにさらわれた妻のシーターを取り戻すまでの奮闘を描いた古代インドの壮大な物語だ。
ラーマ王子には、異母弟にして従者のラクシュマナや猿族の戦士ハヌマーンという強力な旅の仲間がいたが、彼らの旅路は常勝無敗というわけにはいかなかった。彼らは旅の途中で猿族や鳥族といった味方を得ることはできたものの、ラクシャーサ(羅刹)の軍勢との戦いでは、インド神話特有の超兵器によって何度も潰走させられていた。
そんな彼らを助けたのが、インド神話の特色ともいえる神々の名前+アストラ(矢/呪文)と名付けられた数多くの武器だ。
例えば火神アグニの力を宿すアグネヤストラ、暴風神ルドラの力を宿すルドラストラなどで、それらの登場はある種、英雄たちの見せ場ともなっていた。特に創造神ブラフマーの加護を宿すブラフマーストラは強力で、インド最大の叙事詩『マハーバーラタ』でも、第三王子アルジュナや敵軍にいる異父兄カルナ、武芸師範ドローナなど、主役級の英雄、豪傑たちによって使用されている。ブラフマーストラはブラフマーの矢、あるいは投げ槍、あるいは技や術、光線、ミサイルとして表現されているようだ。
神々の化身が神の名を持つ武器で戦う。だからこそインド神話の戦いはダイナミックなのだろう。
インド神話の虚構侵蝕の特徴は、神話世界の再現にある。英雄、豪傑、悪鬼たちは神々の化身としての力を宿し、そのうえ神の名を冠する武具(あるいは呪文)を使って虚構世界の定着を妨害する者たちを薙ぎ払ってくる。きっかけは『ラーマーヤナ』の物語を再現したようなお姫様の誘拐事件やアスラ神族の黄金の都ヒラニヤプラの探索、インドラの御者マータリの地底界遍歴の世界観を踏襲した冒険だったものが、いつの間にか天地を揺るがす戦いになっていたりするのだ。
インド神話の虚構侵蝕事件として最悪だったのが、ブラフマシラス強奪事件だ。ブラフマシラスは、使えば全世界を壊滅させるほどの超兵器で、世界に雷を鳴り響かせ、何千もの流星を落とし、天地を鳴動させるほどの威力を持つ。しかも使用されると12年間も雨が降らなくなり、金属や土などのすべてが毒で覆われるというものだ。
この事件の解決には、大勢の観測者が神との戦いを強いられてしまったという。


『インド神話』(沖田瑞穂 編訳/岩波書店)
『いちばんわかりやすいインド神話』 (天竺奇譚 著/実業之日本社)
『ヒンドゥー教』(M・B・ワング 著、山口泰司 訳/青土社)
『新訳ラーマーヤナ』(ヴァールミーキ 著、中村了昭 訳/平凡社)
『マハーバーラタ入門―インド神話の世界』(沖田瑞穂 著/勉誠出版)
『インド神話 - マハーバーラタの神々』 (上村勝彦 著/筑摩書房)
16世紀にヨーロッパの征服者が到着する以前、中米(メソアメリカ)にはすでに高度な文明が発達していた。彼らは象形文字を使い、天文学に通じ、ジャガー人間を信仰していた。好戦的な狩猟民族との戦いで支配民族が入れ替わることはあれど、文化は受け継がれ、類似した役割を持つ神々が信仰されていたのだ。
14世紀にメキシコ中央高原にやってきたアステカ人は、こうした民族の中では最も後発だった。
アステカ神話によればアステカ人はアストランの地を出発し、狩猟などを行ないながらメキシコ中央高原をさまよっていた。その後、メキシコ盆地に定住し、傭兵としてほかの部族に仕えていたが、政略結婚で贈られてきた部族の姫を生贄に捧げて怒りを買い、追放の憂き目にあってしまう。
しかし追放された島で彼らは三都市同盟を締結。ついには周辺の都市国家や同盟国を征服したのである。しかしそんなアステカ人も、最終的にはスペイン人の冒険家エルナン・コルテスによって征服されてしまった。
そんなアステカ人が信仰していたのがアステカ神話だ。信仰する神は自然に根差した多神教の神で、大別するなら農耕神、天候神、冥界神、火の神のほか、さまざまな自然神であった。神々の中には大地や人間につらく当たる恐ろしい存在もいるが、それもまた中米の厳しい気候や土地の状況を反映したものだったのだろう。
マヤ人が死を恐れていたのとは対照的に、アステカ人の男にとっての戦死、女にとっての出産死、そして人身供儀での生贄としての死は、名誉とされていた。なぜならアステカ人やその先住民は、神々が人間の血を必要としていると信じていたからだ。
神話において神々が自らの血を使って人類を作ったことへの恩義からというのも理由のひとつだが、アステカ人にとっての人身供儀は、宇宙の秩序を保ち、信仰する太陽を強化するための自然の制御方法だったのである。
古代ナワトル語で“羽毛に覆われた蛇”を意味する、人々にトウモロコシ(メイズ)の栽培などを教えたアステカ神話の農耕神。また風の神でもある。
古くは水や農耕に関わる蛇神であったが、後に暦や方位、科学や芸術、工芸などの文明一般を人類に授けた文化神と考られるようになった。
人間としての姿は白い顔の男性とも考えられている。また彼自身はヒスイや鳥、蛇、蝶と言った平和的な供物しか人々に求めず、人々に人身供犠をやめさせたとされている。それゆえに人身供儀を好むテスカトリポカの恨みを買い、酩酊させられて自分の妹と肉体関係を結んでしまった。
これを恥じたケツァルコアトルは、宮殿を焼き払い、宝を埋め、自ら生贄となって火葬されたという。その灰は何羽もの鳥となって空に舞い上がった、あるいは金星に姿を変えて天に逃れたとされている。
なお、ケツァルコアトルには「セーアカトル(一の葦の年)に復活し、帰還する」という予言があった。スペイン人のコルテスがメキシコに来た1519年は偶然にもこの“一の葦の年”であり、そのためアステカ帝国の君主が白人であるコルテスをケツァルコアトルの再来と錯覚、対応が遅れたとする説は有名だ。
アステカ神話における大熊座の神であり、夜空の神。古代ナワトル語では“煙を吐く鏡”を意味する。
魔術を操る軍神として人々に勇気や幸運をもたらしてくれることもあるが、同時に不幸や災害をもたらす二面性のある神格として描かれることが多い。また善神として登場するケツァルコアトルのライバルともされている。
テスカトリポカには赤、青、白、黒の4兄弟神があり、それぞれがテスカトリポカと呼ばれているが、黒神が特にこの名で呼ばれている。
アステカの創世神話は5つの連続する太陽譚から構成されている。最初の太陽はテスカトリポカに支配されていた。この時代は巨人たちが住んでいたが、ジャガーが巨人たちを食べたことで終わってしまった。
第2の太陽はケツァルコアトルが支配した。しかしこの太陽はテスカトリポカの送った強風で破壊され、残った人類も猿に変えられてしまった。
第3の太陽は雨の神トラロックが支配した。しかしこの太陽も火の雨で壊され、人々は鳥にされた。
第4の太陽はトラロックの姉妹であるチャルチウィトリクエが支配した。しかし、この世界も洪水で破壊され、生き残った人々も魚に変えられたという。
第5の太陽は、テオティワカン(神の都)に集まった神々によって創造された。当初、敵対していたテスカトリポカとケツァルコアトルもこの時ばかりは協力し、巨大な大地の怪物トラルテクトリを2人で倒し、怪物の体を引き裂いて天と地にしたとされる。
だがこの世界にはまだ太陽がなく暗かった。そこで神々は大きな火を焚き、神の中から次の太陽になる生贄を選ぶことにした。
それには傲慢で強靭かつ頑固なテクシステカトルが名乗りを上げたが、実際に炎を見ると気後れしてしまったようだ。そのため最初に火に飛び込んだのは、体が弱く、謙虚で弱虫とされていた弟のナナワティンだった。
その結果、ナナワティンは第5の世界の太陽神トナティウとなり、遅れて飛び込んだテクシステカトルは月になったとされている。
しかしトナティウとなったナナワティンは、神々と人間の生贄の血を頻繁に要求する神になってしまった。神々は生贄になる要求を受け入れたが、しかしこの世界にはまだ人間がいなかったので、ケツァルコアトルが地下世界ミクトランに行き、前の世界の人類の骨を手に入れることになった。その骨に神々の血を混ぜることで生まれたのが、第5の太陽の世界の最初の人間の男女だ。
なお、この第5の太陽の時代、すなわち現代もまた、アステカの神話では地震によって滅びると予言されている。
アステカ神話の虚構侵蝕の特徴は血と生贄、太陽信仰、そして繰り返される世界の終末だ。最善の世界を望み、試行錯誤する虚構核には、アステカの創世神話は相性がいいのだろう。
またコアトルの隠した宝を巡って略奪者や人外の神々と戦うというケースも多い。現実世界で発見された出土品は人々の想像をかきたてるだけでなく、出土品そのものが虚構核となって栄光の時代を再現することもあるからだ。現代と違う価値観から作られた虚構侵蝕は、きっと血生臭いものとなるだろう。


『マヤ・アステカの神々』(土方美雄 著/新紀元社)
『世界の神話百科:アメリカ編』(D・M・ジョーンズ、B・L・モリノー 著、蔵持不三也 監訳、井関睦美、田里千代 訳/原書房)
『図解世界の神々と神話』(神話雑学研究会 編著、中村了昭 訳/成美堂出版)
『世界の神話伝説図鑑』(井辻朱美 監修、フィリップ・ウィルキンソン 編、大山晶 翻訳/原書房)
メソポタミア(川の間の土地の意味)神話は、紀元前3000年以上前に、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域で誕生した。この神話は楔形文字で粘土板に刻まれたもので、記録された世界最古の神話と目されている。
なお、メソポタミア神話、あるいは古代オリエント神話とも呼ばれるこの神話群は、現在の神話の形になるまで、いくつかの段階を経ている。最初がウル、ウルク、ラガシュなどといった高度な都市国家を建設したシュメール人が考えたシュメール神話だ。
シュメール神話では、世界は閉じたドーム状になっており、その外には原初の海が広がっていると考えていた。その後、紀元前24世紀頃、アッカド人がメソポタミアを支配し、シュメール神話は彼らの言葉に置き換えられた。メソポタミアの神々が複数の名をもって同様の活躍をするのはそのためである。
やがてアッカド人はメソポタミア南部にバビロニア、北部にアッシリアを築き、言語によりバビロニア神話とアッシリア神話を分けた。この段階でほぼ現在に知られている古代メソポタミア地域の神話は確立したのだが、その後、古代ペルシア王国に飲みこまれ、またキリスト教、イスラム教の創始により、19世紀に石板などが発掘されるまで途絶えてしまった。しかしその息吹は後世の神話の中に息づいており、旧約聖書の創世記などにもその片鱗は見え隠れしている。
シュメール神話における愛と美、戦いと豊穣の女神。都市国家ウルクの守護神。バビロニア神話ではイシュタルと呼ばれ、ギリシア神話ではアフロディーテ、ローマ神話ではヴィーナスと同一視されている。
太陽神ウトゥ(シャマシュ)とは双子の兄妹で、冥界の女王エレシュキガルの妹。
エピソードとしては、姉の支配する冥界をも支配しようとし、冥界の七つの門をくぐった“冥界下り”が有名。門を通るたびに装飾品をひとつずつ奪われたイナンナは、姉の前に到着した時は全裸になっており、“死の眼差し”を受けて死んでしまった。
知恵の神エンキ(エア)はイナンナを蘇らせようとしたが、復活のためには身代わりに誰かを冥界に送らなければならなかった。そこでイナンナは彼女の死に無関心であった牧羊と豊穣の神である夫のドゥムジ(タンムズ)と彼の姉を捕らえ、2人が半年交代で冥界に行くことになった。季節が変化するのはそのためである。
バビロニア神話の太陽神。バビロニアの国家神。知恵の神エンキの息子で、後に最高神アン(アヌ)とエンリルから権力を譲渡され、パンテオン(万神殿)の至高神となった。
バビロニア神話の創世記叙事詩『エヌマ・エリシュ』によれば、神や世界は海水の女神ティアマトと淡水の神アプスーの交わりによって生まれたとされている。しかし新しく生まれた若き神々たちは騒々しく、アプスーは彼らを殺害しようとする。それを察知したのがエンキであり、エンキはアプスーを魔法で眠らせると殺害し、その遺骸の上に神殿を立てた。その神殿で生まれたのがマルドゥクだ。
アプスーの殺害に怒ったティアマトは11体の怪物を生み出して攻め込んだが、エンリルの指名を受けたマルドゥクがこれを迎え撃った。ティアマトの軍勢には神々の運命すらも記した“天命の書版”を持つキングーもいたが、彼はマルドゥクの姿を見ただけで恐れをなし、捕らえられたという。最終的にティアマトは体を引き裂かれ、天地創造の礎となった。
ティアマトの肉体は天と地になり、乳房は山になり、眼からはチグリス川とユーフラテス川が生じたという。またマルドゥクは“天命の書版”をキングーから奪い、神の代わりに労働する者としてキングーの血と骨から人間を創造したとされている。
『ギルガメッシュ叙事詩』は、楔形文字で粘土版に記された古代オリエント最大の文学作品だ。
ウルクの王ギルガメッシュは、強き英雄であったが暴君でもあった。その横暴ぶりを嘆いた市民たちは神々に祈り、女神アルルはギルガメッシュを懲らしめるため粘土から野人エンキドゥを造った。しかし2人の戦いは決着がつかず、ギルガメッシュとエンキドゥは互いの力を認め、親友になったという。
人の心を知ったギルガメッシュは名君となり、シャマシュの加護もあってフンババ退治などを行なったが、イシュタルの求愛を断ったことで女神の恨みを買ってしまう。イシュタルの差し向けた天の牡牛(グガランナ)はウルクで大暴れしたが、これを殺したものは罰を受けねばならかった。
親友のエンキドゥを呪いで失ったギルガメッシュは、死を恐れるようになり、不老不死を求め、エンリルの起こした大洪水を生き残った賢人ウトナピシュテムを求めた。過酷な工程を得て、若返り草を手に入れたギルガメッシュ。だが沐浴中に草を蛇に奪われてしまう。
こうしてギルガメッシュは、限りある命を精一杯生きるのが人間であると悟ったという。
かつての虚構侵蝕は神話こそが題材だった。そのため世界最古の神話メソポタミア神話には、もっとも古い虚構侵蝕を生み出した可能性がある。
古代オリエント界最大の英雄ギルガメッシュは、紀元前27世紀頃、都市国家ウルクに実在したとされる王だ。叙事詩では暴君であった彼が野人エンキドゥとの友情によって名君となったとしているが、それはあくまで物語上でのこと。人々がこうあってほしいと望んだ君主像だったのかもしれないが、現実とはいいがたい。しかし、一度形作られた物語―虚構は、虚構侵蝕と成り得る。想像力が現実になると知った古代人が、虚構侵蝕を利用しなかったとは言い切れない。
彼らは物語で現実を塗り替え、暴君を本当の名君にしたかもしれない。旧約聖書にあるバベルの塔の元ネタとなった神殿(ジッグラド)も、あえて虚構の残滓として残したものかもしれない。
メソポタミア神話は多くの神話の原点であり、神の権能や怪物の生態、アーティファクトの能力の元ネタを多数含んでいる。ゆえに敵対する神や天使、悪魔が真の姿として、メソポタミア神話の神々に変じる可能性も心の隅に置いておかなければならないだろう。


『最古の宗教:古代メソポタミア』(ジャン・ポテロ 著、松島英子 訳/法政大学出版局)
『オリエントの神々』(池上正太 著/新紀元社)
『ギルガメシュ叙事詩』(矢島文夫 訳/筑摩書房)
『シュメール神話集成』(杉勇、尾崎亨 訳/筑摩書房)
『ゼロからわかるメソポタミア神話』(かみゆ歴史編集部 編/イースト・プレス)
『図解世界の神々と神話』(神話雑学研究会 編著、中村了昭 訳/成美堂出版)
『世界の歴史〈2〉古代オリエント』(岸本通夫、伴康哉、富村伝、吉川守、山本茂、前川和也 著/河出書房新社)
フィクションとして、20世紀の作家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトに生み出された、人間が数奇な運命をたどる神話。
それが、この“Cthulhu”神話だ。
このCthulhuは本来人間に発音不可能な音を表記した文字であり、クトゥルフ、クトゥルー、ク・リトルリトル、クルウルウなど便宜上さまざまな読み方があるが、ここでは“クトゥルフ”に統一して説明する。
ラヴクラフトが書いた小説群“コズミックホラー(宇宙的恐怖)”は、そのほとんどがパルプマガジン(安価な大衆向け雑誌)に掲載されており、ラヴクラフト自身は無名な作家のまま、46歳という短い生涯を終えた。
彼の書いた小説群“コズミックホラー”は、彼の死後に友人である作家オーガスト・ダーレスや作家クラーク・アシュトン・スミスによって神話として体系化された。その後、彼らが設立したアーカムハウス社から作品集として出版され、高い評価と絶大な人気を得ることになる。
さらには影響を受けた作家たちがその世界観を使って作品を作り、シェアードワールドとしてより強固な神話へと成長していくことになった。
神話の内容としては、現存する人類史の神話はクトゥルフ神話からの派生であり、人類史の神話のベースとなっている地球を支配していた強大な力を持つ異形の化物(=旧支配者)が現代に蘇るというのがおもたるものになる。
旧支配者のほとんどは人間に敵対的または無関心であり、殺戮や破壊など邪神と呼ぶにふさわしい所業を繰り広げる。
さらには、宇宙から飛来する異形の化物たちもいて、それらは邪神やその眷属として地球の旧支配者と争い、人間はそれに巻き込まれ翻弄されるという、ホラー作品として創造されたにふさわしい、救いのない神話となっている。
神々の争いを利用したり、数少ない人間に味方をする旧支配者の協力を得たりして邪神を撃退する人間も現われるが、それは稀有な例として知られている。
昨今ではTRPGの世界観として広く知られ、ラヴクラフトやダーレスが作り上げたものとは別のイメージを抱かれることも多い。
また、シェアードワールドという環境で創造されたものであるため、神々の能力や設定は作家ごとにさまざまであり、統一されていない場合がある。
この項目に記載された各神格の設定は、一般的に知られているものを採用し、そのほかに存在する設定に関しては簡単に触れる程度に留める。
クトゥルフ神話に登場するドリームランドは、夢の中で特殊な手順を踏むことで到達できる異界であり、そこでは現実世界のことを“目覚めの世界”と呼んでいる。
中世やアラビアンファンタジーのような世界観を有し、我々のような人間以外にも、空を飛び人語を喋る猫や、角と尻尾を持つ人種、さらには神々に由来する神話的生物も多く存在していて、それぞれの領域を守りながら暮らしている。
地球由来の神々“大いなるもの”も隠れ住んでおり、その者たちを守護する神としてノーデンスと、それと敵対しながらも同じく大いなるものを守護する者としてナイアーラトテップが存在する。また、アザトースなどの人間に敵対的な外なる神も関与しており、普通の人間にとっては非常に危険な世界である。
クトゥルフ神話にはさまざまな魔導書があり、時に現実世界に存在している書物が実はクトゥルフ神話に関する魔導書であるといった設定が付与されていることもある。
有名な魔導書としては“ネクロノミコン”“金枝篇”“ルルイエ異本”“エイボンの書”“セラエノ断章”などがあり、そのどれもが強力な力を持ったアーティファクトでもある。
また、これらの魔導書の中には特定の神と密接な関係を持つものもあり、魔導書を所持しているだけで神からの干渉を受ける場合もある。
神話の名称に使用されている神ではあるが、この名称自体は作品名から引用されたものであり、神話の主神というわけではない。しかし、旧支配者の大祭司とされ、人間が到底及ばない神と呼ぶにふさわしい強大な存在であることは確かだ。
タコやイカに似た頭部や鉤爪と水かきの生えた手足、背中にはコウモリに似た翼を持ち、表皮は緑色の鱗か瘤に覆われた、体長数百メートルの巨体という姿をしている。
遥か過去に外宇宙から地球に飛来してきた侵略者の長で、眷属たちとともに当時の地球人である古のもの(異星からの移住者で人類の祖先ではない)と争い、やがて南太平洋の大陸を支配することとなる。
そこに造られた都市ルルイエに眷属たちと住んでいたが、現在はルルイエごと南太平洋に沈んでしまい、死の如く眠っているとされる。
これは“旧神と呼ばれる旧支配者と対を成す者たちによって行なわれた”とされる説もあるが、定かではない。
“万物の王である盲目にして白痴の神”として宇宙の混沌そのものと描かれる、神話において最強クラスの能力を持つ神である。
知性を持たない邪神であり、自身は宇宙の果てに存在するが、配下の神々を操って人類や旧神と敵対している。
ただし、描く作家によってはその設定は異なり、旧神によって知性を奪われた旧神以下の存在に過ぎない設定や、宇宙自体がアザトースの見る夢であるとする設定も存在する。
また、人間や他種族と交わって落とし子を残すこともある。
アザトースの腹心である時間の神。
時間と空間そのものであるとされ、過去から未来まで存在するすべてを内包しており、またそれらと共存している。
始まりも終わりもなく、未来の可能性すらも内包していることから、存在というよりは概念に近い。
しかし、それにも関わらず意志のようなものは存在し、人間や旧神と敵対している邪神である。
まれに人間と交わり、その落とし子を残すことがあるが、その能力はヨグ=ソトースには遠く及ず、普通の犬に敗北した事例もある。
旧支配者の一員として“風”を象徴する神である。
ヨグ=ソトースの息子であり、“名状しがたかいもの”という異名を持ち、その姿がどのようなものであるか詳細は不明である(大気そのものゆえに不可視であると考える者もいる)。また、“黄衣の王”と呼ばれる怪物はハスターの化身であるとも言われ、ハスター自身のことを黄衣の王と呼ぶこともある。
クトゥルフとは敵対関係にあり、かの神が眠りについたあとも眷属同士での小競り合いは絶えず、人間がそれに巻き込まれ犠牲になる場合も多い。
この場合の眷属には同じ風の属性を持つ“イタカ”や“ロイガー”など、神と呼ばれるにふさわしい能力を持つ者がおり、もし本格的な争いが始まれば人間にも相当な被害が出ることが推測される。
現代のコンテンツ、特にユーザーが想像力を働かせるTRPGにおいて題材とされることが多く、その柔軟性から今も多種多様なローカル設定が付け加えられている“成長中の神話”。
それゆえに、これを題材として発生する虚構侵蝕は小規模ながらも多種多様であり、宇宙的存在による侵略から消失した人間の捜索、自己の掘り下げなど枚挙にいとまがない。
だがなぜ、いち作家から始まったシェアードワールドに過ぎない神話が、これほどまでに受け入れられるようになったのか。
ラヴクラフトの死後、ダーレスやカーターといった作家たちがなぜそこまでこの神々に惹かれることになったのか。
クトゥルフ神話そのものではなく“クトゥルフ神話が拡大していく”状況こそが虚構侵蝕かもしれない。


『ラヴクラフト全集1~7』(H.P.ラヴクラフト 著、大西尹明 訳/東京創元社)
『クトゥルー〈2〉永劫の探究』(オーガスト・ダーレス 著、大滝啓裕 訳、岩村光博 訳/青心社)
『ゲームシナリオのためのクトゥルー神話事典 知っておきたい邪神・禁書・お約束110』(森瀬繚 著/新紀元社)
『クトゥルー神話事典』(東雅夫 著/学研出版)
『クトゥルフ・ハンドブック Horrorロールプレイング・ゲーム完全入門書』(山本弘 著/ホビージャパン)
『クトゥルフ神話ガイドブック: 20世紀の恐怖神話』(朱鷺田 祐介 著/新紀元社)